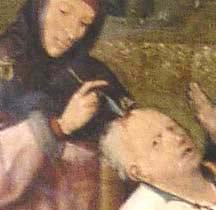|
愚者の花――ボス
初夏を思わせる陽射しが降りそそぐのどかな田園風景の中で、いま、奇妙な手術が行われている(図1)。白い上っ張りに赤いズボンの太っちょ男は、額から小石を取り除かれているところだ。麻酔もかけない野外手術だから、その痛みに耐えられないのだろう、白い布で椅子に縛られ、訴えかけるような悲壮な面持ちで後ろの医者をうかがっている。片やその医者たるや、漏斗を逆さに被って頭巾を覆い、腰には陶器の水差しをかけているといういでたちで、何やら胡散臭い。いかさま師らしきは、この医者だけでなく、「おお、素晴らしい」と、まるで大げさに感嘆の声を上げているような司祭、「ふ~ん、どうかね」と言わんばかりにその成り行きを見守っている女も、あやしげである。司祭の方は錫製水差しを持ち、女の方は丸いテーブルに肘をついて赤い本を頭に載せて、赤い布製の巾着のようなものを腰からさげているといったありさまだ。
澄んだ大気に山の連なりがはるかに見え、朝露に濡れたように輝く緑野には教会や風車が点在している。涼やかな風の薫りさえ漂うこの光景をくりぬいて、黒地に金字の見事なカリグラフィーが丸く周囲を飾っている。それは、まことしやかに、この男の状況を伝えている。
「先生、どうか石を取り除いておくんなさい。おいらの名はルッベルト・ダスだ。」
15世紀から16世紀にかけて活躍したヒエロニムス・ボスほど、怪奇な作風で知られた画家はいないであろう。宗教画をもっぱらとしながら、植物、動物、人間を組み合わせた摩訶不思議な生き物や怪物を数多く描き、かつては「悪魔メーカー」の異名もあった。今日オランダに属する郷里スヘルトーヘンボスからほとんど外に出ることなく、ひたすら魔界と人間の愚行を描き続けた画家である。あまりに怪奇的、魔術的な作品ゆえに、異端的な宗教団体「自由精神兄弟会」に属するとか、魔術や錬金術に長けていた、など、彼をめぐってはさまざまな解釈がなされ、初期ネーデルラント美術史を賑わせてきた。
それでも彼のイメージの源泉については、中世の教会堂を飾っていた彫刻や写本の挿絵などが指摘され、また郷里の風物や祝祭、出来事や事件もインスピレーションを与えたと言われて、近年は、敬虔なキリスト教徒であったという一応の見解が定着している。しかし、この月並みな見解が定着してもなお、その火種はくすぶり続けている。
ボスの中でもこれは決して怪奇な作品ではなく、いかさま治療師らの策略に見事まんまとひっかかって、すでに財布を破られている愚かな患者を描いた諷刺画である。そもそも「ルッベルト」(lubbert)という名前は、「欺かれた、去勢された穴熊」の意という。さらに「どうか石を取り除いておくんなさい」とルッベルトが嘆願するネーデルラントの言葉のうち、「石」は“Keye”(小石)という語で書かれていて、「愚かだ」を意味する言い回し「頭に小石をもつ」と関わっている。ネーデルラントでは、中世から17世紀にわたって、頭の中の小石が大きく成長すると愚かになる、とされ、その石を切除するのは愚者の治療とみられていたのであった。
こうして画面は、司祭に妻を寝取られた愚かな夫が、彼らにそそのかされて、その原因である「石」を切除される情景を描き出している、と解釈されているのである。
しかし、かわいそうなルッベルト・ダスが叫ぶものの、彼の頭から取り出されているのは小石でも大きく育った石でもない。花弁の細く分かれた花なのである(図1-1)。チューリップとされているこの愛らしい花は、テーブルの上にも置かれていて(図1-2)、もう、すでに二つの石、いや2本の花が取り除かれたことがわかる。ネーデルラント語の語源、言い回しや格言などを詳らかに調べ上げて大著をものした16世紀のコルネリウス・キリアヌスの『語源学辞典』によると、チューリップ(Tulipe,tulpe)はまた「愚か」を意味する言葉とされていて、石と置き換えられても不思議はないのである。しかし15世紀末期に、果たしてチューリップはネーデルラントに移植され、栽培されていたのだろうか。チューリップは、実際には16世紀半ばに当地に持ち込まれ、もっとも古いチューリップの絵は、植物や動物を描いて名をはせた博物学者コンラート・フォン・ゲスナーの『ドイツ植物園誌』(1561年)の図版とされているから、ボスの時代から半世紀下ってからのことである。またキリアヌスによると、チューリップは“keyken"(小石)という名の「撫子」をさす言葉であったというから、画面に描かれているのは、撫子という説もある。
この作品がたしかにボスの真筆であるか否かを問われているのは、いずれにせよ、このチューリップと見られている花ゆえばかりではない。周囲の見事なカリグラフィーがボスの他のどの作品にも見られず、当時、これと同じ主題の作品を所蔵していたユトレヒトの司教の記録にも、詳細はおろかボスの名前さえ記されていないからである。それでも、澄んだ大気に溶け込んだ細やかな自然描写、人物の巧みな表情にはボスの才が見られ、おそらくはボスの原画に手を加えたか、あるいは原画にもとづいた後世の作品とみるのがふさわしいのであろう。そして何よりこの作品が、人間の罪と愚行を、辛辣でありながら哀愁をこめた笑いをもって異色の絵画世界に展開した画家、ボスの精神からほど遠からぬところにあるのは間違いあるまい。
愚者の石――ブリューゲル
ところで、初期ネーデルラント絵画を担う画家たちの中では、ボスとともにひときわ異彩を放つピ-テル・ブリューゲルもまた、「愚者の石の切除」を描いている。「農民の画家」との異名をとったブリューゲルは、むしろ当時の知識人のひとりであり、宗教改革と宗教戦争に翻弄された時代の愚行を鋭く諷刺した画家とみられるようになっている。
彼はアントウェルペンの印刷出版業者ヒエロニムス・コックの店〔四方の風〕で版画の下絵を数多く制作した。当時、版画は今日の出版とかマスメディアと同じく、いわば知識と情報の伝達の手段であり、ジャーナリズムの機能も果たしていた。アントウェルペンは、聖書の多国語訳や宗教的パンフレット、そして地図や博物学といった新しい時代を担う出版のメッカであり、世界有数の商業取引が行われていた国際都市であった。この都市から発信された出版物は、時代の趨勢をとらえるばかりでなく、時代の流れをも変えていったのである。
コックの下で印刷された銅版画には、ボスの作品にもとづく版画も多く、実際「ボス」の署名入りで出版されている。それはボスの人気が、一世代のちになってもいかに高かったかを物語っている。それらの中に、ブリューゲルの下絵になる「愚者の石」をテーマにした銅版画が二点ある。ひとつは「マレヘムの魔女」、もう一点は「ロンセの長老、あるいは愚者の石の切除」である。いかにも山師らしい行為が、実は魔術と結びついているとみられていたことを示すのが「マレヘムの魔女」だ。
画面では、大きく口を開け、目を見開き、あるいは何か叫んでいる愚か者たちが、頭から石を取り除いてもらおうと、マレヘムという名の町に住む魔女のところに押し寄せている。中には、こぶし大に大きく成長した石を頭上に載せて、その重みになす術もなく両脇を支えられている者もいる。また画面右下では、大きな卵の中に入った愚か者が、額からいくつもの小石を出してもらっている。ボスの作品と比べると、卑俗で猥雑な情景が描き出され、カリカチュア化されているとはいえ、おそらく16世紀の民衆の姿を存分に伝えているのだろう。しかし「マレヘム」という町は実存せず、その名は「狂人」を意味する「mal」と、「人の住むところ」を意味する「gem」の合成語であるという。マレヘムとは、つまるところ、人間の住む場すべてをさしているのかもしれない。
では果たして、実際にこのような手術が行われていたのだろうか。当時は、イタリアでの医学と解剖学の発展はもとより、北方とくにこのネーデルラントの地では、自らの手で人体解剖を行って『人体の構造について』を著した近代医学の父アンドレアス・ヴェサリウスが登場した時代である。記録はひとつ、1571年に、現ベルギーのヘントに住む12歳の狂気の少年の頭から石を取り出す手術が行われたという公文書が確認されている(その少年がその後どうなったかは知る由もない)。おそらく、中世において医学を担っていた医学校および修道院から医術が拡大し、市井の刃物をもつ職業とくに床屋外科医や、少しばかりの知識を持つ人物らが、耳学問でこのおそるべき治療を施すという現実があったのだろう。民間療法の中にはむろん、優れた知識をもつ者もいたであろうが、迷信に満ちた民衆世界で彼らが行った医術は、治療とは遥かにかけ離れた術であり、ときに魔術や妖術と結びついて異端審問に問われることもあった。近代医科学の幕開けには、多くの秘められた歴史があるのである。
そして、えせ医師たちの暗躍を物語るように、1500年を過ぎた頃から、いかさま治療を扱った絵画や版画、文学が登場する。それらは、山師の貪欲さとそれにだまされる民衆の愚かさを諷刺したもので、民衆演劇の格好のテーマにもなっていた。ことネーデルラントに限っていうならば、15世紀から修辞家集団(レーデレイケルス)という演劇・文学組織の活動が盛んとなり、市民のために詩の朗読や音楽や演劇を催す娯楽団体であったそれらは、やがて各都市に母体をもち、団体固有の名前や紋章をつくり、祝祭のときや縁日、市の立つときなどに、趣向を凝らした山車や舞台を組んで上演した。15世紀ブルゴーニュ公国の黄金時代以降は、コンクールを催して優れた詩人や劇作家を産み出している。さらに神聖ローマ皇帝カール5世と、次代のフェリペ2世の時代になると、彼らの圧政を揶揄したり、民衆を煽動したりする力を有するまでになっていったのである。演劇が往々にして時の前衛となるように。
彼らの戯曲は当時の文芸を解釈する上では欠かせないものといえよう。宗教劇の合間に上演された笑劇や、宗教行列の一環として繰り広げられた行列(Procession)も、中世のみならず、ほぼ全時代にわたって宗教芸術と民衆芸術を理解する上では、実に重要なものである。しかし、いかんせん、こうした時間とともに展開し、終焉する芸術は、痕跡が残りにくい。衣装や舞台芸術は、上演が終われば取りはずされ、また再度利用されようとも、のちのち長く残る可能性は少ない。文字資料が残っていれば、とても運がよいほうなのである。
この「愚者の石の切除」も、こうした笑劇や大道芝居として上演されていたのではないかという指摘がある。実際、1563年にアントウェルペンで催された世俗行列(オメガング)の山車では、「脳みそなし」が「藪医者」から石を取り出してもらっているという活人画があったという。キリアヌスによると、そもそも小石Keye あるいはKeyaerd は、異常をきたした脳とか、狂気の、妄想的な脳みそを意味したという。一方、「愚か」「阿呆」を意味する“sot”と「球」“bol”が組み合わされた“sottebol”は、頭が球の形をしている愚か者として、これまた画題となっている。
つまるところ、球体をした石は頭の形にたとえられ、それは狂気と愚者の象徴とみなされたのである。丸く太り、丸い頭をもったルッベルトは、まさしく愚者の権化として描かれているのだ。まるで言葉遊びのような世界であるが、言葉が人々の思考を直に伝え、それを育んだ精神文化風土を伝えるのであるなら、そこに、人の営みが織りなす歴史の真相が潜んでいるのは確かであろう。
|
|

(図1)ヒエロニムス・ボス、愚者の石の切除 1475-80年 マドリード、プラド美術館 筆者撮影
▲画像クリックで拡大
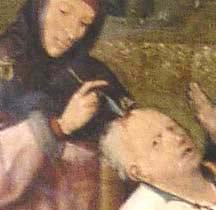
(図1-1)

(図1-2)
|
|
愚者の石と賢者の石
ブリューゲルの作品、ないしはそれに基づく銅版画として語られる「ロンセの長老、あるいは愚者の石の切除」は、もうひとつ別の愚者の石の歴史を教えてくれる(図2)。「ロンセ」は今日ベルギーに残る町で、ここの聖ヘルメス教会という異教的な名の教会に巡礼すると、「愚か」が直るとされていたのだ。今日でも年に一度、愚者の祭りが催され、またこの教会に詣でると精神的病が治るとされている。なおロンセの長老の中には、1554年まで、恐ろしい異端審問官ペトルス・ティテルマンスがいたともいう。
版画では、竈や炉がしつらえられたあやしげな実験室風の部屋での手術が展開する。椅子に縛られてのた打ち回る患者の額から、物知り顔にやっとこで小石を抜き出す長老(図2-1)や、椅子に縛られるのみならず目隠しをされた患者の額を、実験器具のような筒を被った長老が小刀で切開する図(図2-2)が描かれている。壁にかけられたボール、カーテンで仕切られた奥の間に見える炉や実験器具、そして、ほぼ中央で「ふいご」を吹いて何かを熱している狡猾そうな老人(図2-3)。それらすべてが、いかさま医師というより化学者、しいて言えば秘儀的な術をもっぱらとする術師のように見える。事実、16世紀には「ふいご吹き」と呼ばれた一群の錬金術師たちがいた。
古代エジプトに起源をもつ錬金術は、アラビア世界とビザンティン世界、そして、とくに宗教と人種の坩堝であったスペインを介して12世紀にはヨーロッパに伝えられ、中世後期にはヘルメス哲学とカバラと並んで諸学問に大きな影響力をもつに至っていた。錬金術は胡散臭い、といった見方は、おそらくいまでも根強いであろう。それは「錬金」という言葉自体がいかさま的なニュアンスをもつためであろうか。卑金属から金を造る、と解釈されがちなこの「学問」は、いわば今日の学問分野とは与しえないさまざまな要素を包含した化学であり、医学であり、また精神修養の「術」といったらよいだろう。近代科学の知識と目をもってこの術を眺めるとき、それは途方もない誤謬、無知であり、詐欺師的な行為と映る側面もたしかにもっている。しかし、化学的には金属を反応させて新たな物質を造る技術であり、医学的には病を治療する術であり、また精神的にはより安定した状態、いわば癒し、解脱を得るための術、といえる。中世人は、錬金術をこうした万能の秘学として棲まわせることのできる豊かな心の襞をもっていたように思える。しかし、この超域的な学術をいぶかしく思う傾向は、時代を下るにつれていや増してゆき、「超域」という名称が学問分野に使われ始めている今日のアカデミックな世界でも、深く巣くっているようだ。
さて、ブリューゲルの時代には、もはや「錬金術師」(Alghe mist)は「すべて失敗である」(Al ghemist)と絡めて、揶揄と批判の対象になっていた。ブリューゲルの代表作といわれる銅版画「錬金術師」では、ふいごを吹いて炉を燃やし、金属変成に余念がない錬金術師が描かれている。そこでは、全財産をこの錬金術に投じ、すっからかんとなってなお実験を続ける彼の姿と対照的に、早々とこの術をあきらめて家族を連れて救貧院に向かう男が窓の外に見える。錬金術の本来のあり方から暴走し、金を得ようとやっきになるえせ錬金術師たちが横行した時代なのである。「ふいご吹き」と呼ばれた彼らは、また「狂人」の象徴でもあったのだ。
ところで、錬金術のきわめて重要なポイントは「賢者の石」を得ることにある。「賢者の石」は、実験上では硫黄と水銀を過熱して融合させてできる粉末のことであり、象徴的には、前者がもつ男性的原理と後者の女性的原理を融合させて得られる人間と自然との合一のための秘薬であった。この「賢者の石」を得るために、まずは、ふいごを吹いて炉を加熱し、フラスコの中で融合するこの物質から立ち上る蒸気をうまくろ過しなければならない。溶鉱炉、ふいご、フラスコは、錬金術にとって不可欠の器具だったのである。そしてまた、「賢者の石」が象徴的意味をもつように、フラスコは人間にたとえられて、内部で立ち上る蒸気はフラスコの上方、すなわち人間の頭の中で、「賢者の石」を育むと考えられた。そもそも頭脳をもってしてこの術が行われるのだから、頭を「賢者の石」にたとえるのは、彼らにとってはしごく当然の比喩であった。「石」は、こうして一方で、賢者の象徴と捉えられていたのである。
この錬金術の奥儀を会得した中世の人物として、私たち一般の者にも知られているのは、おそらく14世紀のパリで活躍したニコラ・フラメルではなかろうか。写字生として公文書の写しなどを行って生業を立てていたフラメルは、ある日、『アブラハムの書』というヘブライ語の大著を発見し、その解読のためにスペインに旅行して、そこに記されていた錬金術の奥義をユダヤ人から知らされる。何度も失敗を繰り返したあげく、彼は「賢者の石」を得ることに成功して巨万の富を築くばかりでなく、不老不死となって今もどこかに生きている、という。
しかし実のところ、これは16世紀になって書かれた書物から紡ぎだされた伝説なのである。フラメル伝説が登場したこの16世紀は、まさしく錬金術黄金時代であり、かつ近代科学の夜明けであった。迷信と妄信に導かれた術と、理性に導かれた学問とが、ふるいにかけられた時代である。その明暗のはざまに浮上したさまざまな秘儀秘教集団や多くの錬金術師がそのふるいにかけられて、ヨーロッパの闇に吸い込まれていった。それでも、かの薔薇十字団として実を結ぶばかりでなく、数々の著名な錬金術師がネーデルラントも含めた各国で名を残した。そして印刷出版業の中心地アントウェルペンでは、錬金術の著作が出版されるばかりでなく、ネーデルラントの統治者フェリペ2世も、宗教弾圧に凄腕を見せて恐れられたグランヴェル枢機卿も、自身、実験室をもち、錬金術師を雇っていたという。錬金術師を迎え、また実験室を設備する慣習は、すでに中世の宮廷、修道院、教皇庁など、聖俗両界で行われていたことであるから驚くことはないが、ここで特筆すべきは、彼らがボスとブリューゲルの作品を熱心に蒐集した、という事実であろう。
こうした関連付けが得てして疎んじられているのは確かである。それでも、ボスとブリューゲルの周囲になおも火種がくすぶり続け、彼らの不思議と魅力の源泉となっていることは否定できまい。ボスのルッベルトは、「賢者の石」が「愚者の石」へと変貌し、理性と狂気が交錯する時代の幕明けを告げているのである。
|
|

(図2)原画ピーテル・ブリューゲルに帰される「ロンセの長老、あるいは愚者の石の切除」銅版画(彫版師不詳)1557年
▲画像クリックで拡大

(図2-1)

(図2-2)

(図2-3)
|
|
|
主要参考文献
- Cornelius Kirianus, Etymologicum teutonicae linguae:siue Divtionarium teutonico-latinum...., Antwerpen,1599.
- Luis Peñalver Alhambra, La extracción de la piendra de la locura del Bosco o la cura de la melancholía, Reales Sitios, Revista del Patrimonio Nacional, No.133,1997,pp.44-50.
- Madeleine Bergman, Hieronymus Bosch and Alchemy,A Study on the Saint-Anthony Triptyque, Acta Universitatis Stockholmiensis 31,Almgvist&Wiksell International Stockholm,1979.
- Louis Lebeer, Catalogue raisonné des estampes de Bruegel,Bibliothèque Royale Albert 1er, Bruxelles,1969.
- J.van Lennep, Art & Archimie,Etude de l'iconogoraphie hermétique et de ses influences, Editions Meddens,1966.
- Roger H.Marijnissen(collaboration)Peter Ruyffelaere, Jerome Bosch,Tout l'oeuvre peint et dessiné, 1987.Fond Mercator,Antwerpen.
- Henry meige, L'opération des pierres de tête, Æsculape,No.3,mars 1932.
- 高階秀爾編著『ヒエロニムス・ボス全作品集』、中央公論社、1978年。
- 森洋子「ボス、ブリューゲル」『世界美術全集』10巻、集英社、1978年。
- 森洋子「ブリューゲルと民衆の笑い」『形の文化誌[10]笑う形』、2004年、26-51頁。
- 「ペーテル・ブリューゲル版画展」 神奈川県立美術館、東京新聞、1972年。
- 「ピーテル・ブリューゲル全版画展」石橋財団ブリヂストン美術館、東京新聞編、1989年。
- ナイジェル・ウィルキンス 『ニコラ・フラメル 錬金術師伝説』 小池寿子訳、白水社、2000年。
|
|
SPAZIO誌上での既発表エッセー 目次
- 身体をめぐる断章 その(1)――足 no.52(1995年12月発行)
- 同上 その(2)――足―下肢 no.53(1996年7月発行)
- 同上 その(3)――背中(1) no.54(1996年12月発行)
- 同上 その(4)――背中(2) no.55(1997年6月発行)
- 同上 その(5)――乳房 no.57(1998年6月発行)
- 同上 その(6)――手―創造の手 no.58(1999年4月発行)
- 同上 その(7)――手―癒しの手 no.60(2001年3月発行)
- 同上 その(8)――手―不信の手[身体の内部へ] no.61(2002年4月発行)
- 同上 その(9)――剥皮人体 no.62(2003年4月発行)
|