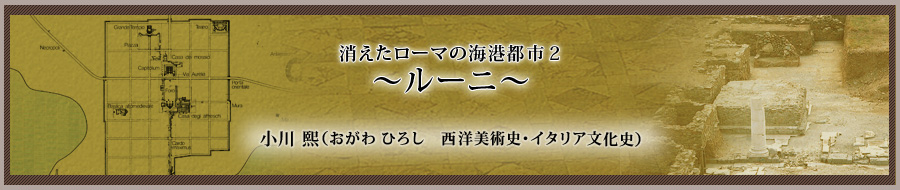石の戸籍
日本人ならだれしも、初めてイタリアの都市を訪れたとき、石をふんだんに使った建築と、その外面を飾る石造の人間像の多さに圧倒されるだろう。私が最初にローマの街を歩いたときも、なるほどこれが石の文化なのかと実感させられた。そしてやがてさまざまな石の建築や美術館にある石彫を仔細に観察するようになると、石にもいろいろな種類があり、石材に関する知識がこれまでなんと乏しかったのだろうと思い至ることになった。
ところがその後ローマ国立博物館の詳しい図録を調べていると、古代彫刻の素材として、大理石などの「戸籍」、つまり産地や種類が明記されているのを知って感激した。有名な作品の例をいくつか挙げると、<ニオベ>(図1)や<ランチェロッティの円盤投げ>(図2)(青銅からの模刻が複数あり、ここではローマ国立博物館所蔵のもの)の素材はいずれも「パロス島の大理石」(marmo pario)と記され、ドイダルス作と推定されている<うずくまるヴィーナス>(図3)は「ギリシア島嶼」(marmo insulare)となっている(marmoはイタリア語で「大理石」)。パロスというのはエーゲ海の真中にある島で、ここで産出する良質の白大理石はイオニア時代から神像彫刻などに使われていたことで有名である。パロスのほかにもキオス島などエーゲ海には大理石を産する島がいくつかあり、上記の「ギリシア島嶼」というのは、そのうちのどこかが特定できないということだろう。
以上の3点は、いわゆるヘレニズム期の代表的な彫刻であり、いろいろな経緯によって前1世紀頃にローマにもたされたものであるが、ここでは美術様式に関することには触れないこととしても、ローマをはじめとするイタリアに現存するヘレニズム彫刻の制作については、かなり複雑な状況があることに言及しておきたい。というのは、ローマがギリシアをも征服した共和政時代には、ギリシアですでに神殿などに設置されていた石彫をローマに移送したものもあれば、石材をイタリアに運んでから、ギリシア人の彫刻家に制作させた場合もあると考えられるからだ。そのことは、明らかに帝政時代に入ってからの彫刻でも、ギリシアの石が使われていることから推測される。例を挙げるなら、ローマ国立博物館の<カラカラ帝頭部>(図4)の素材は「ギリシアの白大理石」( bianco)であり、同じく<大神官アウグストゥス像>(図5)は身体部は「イタリアの大理石」(italico)だが頭部と腕の部分は「ギリシアの大理石」(greco)で接合されている。この時代の彫刻家は、もはやギリシア出身の作家とはいえないかもしれない。なおギリシアの大理石としてはアテネ近郊のペンテリコン産の白大理石(pentelico)、エウヴォイア島の緑白色のシポリン(cipollino)、ペロポネソス半島のテナロン産の「古代赤大理石」(rosso antico)などがあり、後にまた触れることになる。
ところで図録にしばしば出てくるmarmo lunenseというのが初めわからなかった。たとえばやはりローマ国立博物館の<ハドリアヌス帝頭部>(図6)や、あのエロスの極限のような<眠るヘルマフロディトス>(図7)などがこの石材で作られていると注記されている。lunenseというのは形容詞に違いないが、詳しいイタリア語の辞書にも出ていないので全くお手上げであった。ところがある時、ラテン語の辞書を手がかりに、これがLuniという地名の形容詞であることがわかった。しかしこれがまた初めて聞く名前なのであるが、地図で調べてようやく納得が行ったという次第である。Luni(ルーニ、古代名Lunaルナ、以下ルーニと表記)とはイタリア最大の大理石産地であるトスカーナのアプアーネ山地(Alpi Apuane)の近くにあって、そこで産出した石材を集荷・搬出するための港として、ローマ時代に栄えた都市だったのである。現在ではより採掘地に近い場所の名を取って「カッラーラCarraraの大理石」と呼ばれるが、古代にはこの都市は存在しなかったから、それが「ルーニの大理石」であったというわけだ。私の戸籍調べもようやくここまで辿り着くことができた。
ローマ=リグーリア戦争
前置きが長くなったが、まずルーニの位置を詳しく説明すると、イタリア半島西北部のティレニア海に注ぐ、あまり大きくないマグラ河(Magra)の、その河口からわずか3キロほどの左岸にある。まさにトスカーナ州とリグーリア州の州境ぎりぎりのところだが、ルーニは現在のリグーリア州内にあって、行政的にはオルトノーヴォOrtonovoという小さな町に属している。もうひとつの別の言い方をすると、ルーニは古代ローマのアウレリア街道(Via Aurelia)の上にあった。前3世紀の執政官ガイウス・アウレリウス・コッタによって建設されたこの街道は、ローマのアウレリア門(現ポルタ・サン・パンクラツィオ)を出て、初めピサまで開通(前241年)したあと、前109年にルーニを通過し、最終的にはアルルまで延伸されたいわゆる執政官道路の一つである。ローマ軍がティレニア海沿岸のカエレ、タルクイニアなどのエトルリア諸都市を次々に征服して北上し、ジェーノヴァを中心とするリーグリ人を斥け、ガリアまで侵入した際の軍事的基幹道路であった。なおピサ以遠はこれを建設した執政官アエミリウス・スカウルスの名に由来するアエミリア・スカウリ街道と命名されていた。現在はジェーノヴァまですべてヴィア・アウレリアと呼ばれ、国道1号線(SS1)に指定されている。1967年から12年間ローマで過した私は、実は終わりの8年ほど、ローマの城外を出てすぐのあたりのこの国道近くに住んでいて、アウレリア街道は私にとっての生活道路であったのだが、その先(399キロ)にルーニがつながっていることを知ったときもまた、感慨深いものがあった。なお話は飛ぶが、西ローマ帝国滅亡後の中世には、この街道は北方からローマ、さらにはエルサレムの聖地に向かう巡礼者のコースとしての役割を果たし、要するに2,000年間にわたって使われ続けてきたことになる。
さて、この地におそらく石器時代から住んでいたのはリグーリア人(リーグリliguri)という先住民族であった。現在もジェーノヴァを州都とするリグーリア州にその名を残すのだが、文字をもたないこの民族の文献・考古資料は少なく、実態はほとんど解明されていない。ただ河口の港は早くから機能していたと思われ、ローマの文献によれば、ギリシア人がおそらく通商のために寄港していたらしい。かれらはこの地を「セレネSelene(月の女神)の港」と呼び、ローマ人がその意を継承してルナLunaと名づけたといわれる。半月形の地形のイメージがその由来ではないかという説がある。
そして前2世紀の初めにローマ人が到達し、数十年にわたる「ローマ=リグーリア戦争」の末、勝利したローマが植民市を築く(前177)。史家リウィウスによれば、2,000人のローマ市民(多くは退役軍人と思われる)が移植し、周辺の土地を与えられた。この時期、急速に人口が増大したローマでは食糧不足が政治的問題となり、ルーニはその解決のための農業生産の役割を担ったのである。
白亜の港
しかしルーニの繁栄は、帝政期に始まった、背後に広がるアプアーネ山脈の大理石の採掘によってもたらされる。先住のリグーリア人やエトルリア人が全く無関心だったこの宝の山に、ギリシアの大理石文明に魅せられていたローマ人が飛びついたのは至極当然のことだろう。今日「カッラーラの大理石」と呼ばれる石材の美しさについては、ストラボン、プリニウス、リウィウス、ユーウェナリス、スウェトニウスなど、ローマの作家たちが口を揃えて語っているという。特に「スタトゥアリオ」(statuario)と称する白大理石は殊に彫刻用として珍重された。後代のミケランジェロがここに長く滞在し、石切り場で自ら石材を選んだのは有名な話である。そんなわけで前1世紀中葉からローマ人によって採掘が始められ、帝政期に本格化する。アウグストゥス帝はローマの都に、権威にふさわしい美しさとモニュメンタリティを与えるため、各地の大理石を集めて積極的に都市改造を行ったが、とりわけ美しいルーニの白は自らの肖像彫刻のために用い、市内の重要な地点に配置させた。「アウグストゥスはローマを煉瓦の町から大理石の都市に変貌させた」(スウェトニウス)。事実、それ以前のローマの建築に最も多く使われていたのは、トラヴェルティーノtravertino(石灰華、トラバーチン)というティーヴォリ近郊の平地から多量に採取できる比較的安価な石材であり、コロッセオやマルケルス劇場などの遺跡で見ることができる。そのほか、パラティーノの丘の構造物、カンピドリオ、ミルヴィオ橋、ポンペイウス劇場などの大型の建造物には、いずれも各種の凝灰岩が使用されていて、これらの産地はすべてローマに近い現在のラツィオ州であった。つまりこれらの石材は、建材には適しているが灰色や薄茶色だったりして美しさには欠けるものなのだが、一般的に、重量のある石の場合、近距離のものを用いるのが最も経済的であるのは論をまたないだろう。ちなみに、イタリアに限ってさえも、各地のロマネスク寺院などの石材の色彩や質感が地方によって異なることに気づくはずだが、様式的特徴とともにそうした即物的要素を知ることもまた文化史的理解につながるかもしれない。
次代のティベリウス帝によってルーニは国営化される。現場で重労働に当ったのはもちろん奴隷であった。作業には鑿(のみ)や大槌、鉄の梃子(てこ)、楔(くさび)などが用いられ、切り取られたブロックは木製の「滑り台」で山麓に下ろされ、そこから四輪車にのせて牛に牽かせて12キロほど離れた港まで運んだ。
ルーニの港は先に述べたようにマグラ河の河口の左岸にあったのだが、この付近はご多分にもれず積年の砂の移動によって地形が変り、いまはほとんどあとかたもない。近年の調査によれば、喫水1メートルを超えない船ならば着岸できる波止場が存在していたことが確認されている。ローマ人は初め前2世紀頃にはスペインに向かう船の寄港地として利用し、ついでリグーリア人との紛争が起ると海軍基地として機能させたが、かれらを征服したあとは、背後の農地で産出するワイン、チーズ、木材などの輸出のための商港に姿を変えた。そして1世紀以降、最も主要な貨物が大理石となったのである。石材の輸送は陸路で行われたこともあったらしいが、それは時間と労力を要するものであり、多くは石材専用に設計された大型船(ラテン語lapidaria navis)でオスティア港(前69号参照)に向かい、そこからローマに運ばれた。なおこの船の形式はギリシア由来と考えられる(Olaf Hoeckmann :La Navigazione nel Mondo Antico)。さらに近年の海中考古学の発達によって難破船の残骸が発見され、プロヴァンス地方など西方にも輸出されていたことが確認されている。
2,000人の植民から始まった都市ルーニの人口は、帝政期には5,000人ほどに膨らみ、ティレニア海有数の商業都市にふさわしい体裁を整えることになる。いまは完全に廃墟となったその都市の全容について記す前に、その後の運命について簡単に語ろう。
3-4世紀にローマ帝国自体が経済的危機に陥るとともに、必然的にルーニの大理石の需要も下火となった。キリスト教が公認され、西ローマが滅びてビザンティンの支配になると、異教の神殿や神々の彫像が造られることがなくなったことも石材産業の衰退に追い討ちをかけた。ただ、東方教会はいち早くルーニに司教区を置き、中世にも辛うじて地方都市としての存在意義が保たれた。これはオスティアや、ましてポンペイなどとは異なる状況である。その後、西ゴート族(552年)、ランゴバルド人(643年)、ノルマン人(860年)、サラセン人(1016年)に相次いで侵略を受けるのだが、いずれも占領が長期化することなく生き延びたのは不思議なことでもある。いずれにしても、ティレニア海の好位置を占めるルーニのような港湾都市が海上制覇をめぐる諸民族の紛争の絶好の舞台となるのは、歴史地理学的によく理解されることだろう。
さらにはすでに述べたように、マグラ河の河口周辺の地形の変化が進行して港湾の機能は失われつつあり、加えてここでもオスティアと同じくマラリアの発生によって人口が減少する。代って内陸部に新興の中世都市が生まれており、教皇インノケンティウス3世は1204年に河口から20キロほど遡ったサルザーナSarzanaに司教座を移転した。これはいわばルーニの公的な死の宣告であり、以後ルーニは歴史から姿を消すのである。
ここでルーニ遺跡の発掘調査の経緯について述べておこう。ミケランジェロの例でわかるように、ルネサンス期に古代彫刻が再発見されると、アプアーネ山地の大理石にふたたび曙光が当てられ、採掘が再開されるが、それに関連してルーニの廃墟への関心が高まる。遺跡に放置された建築の部品を他に転用するための持ち出しなども早くから行われていたが、17-18世紀には古代文明そのものへの関心から、知識人の間に考古学的な研究態度が生まれ、いわば好事家的な遺物の収集が始まる。本格的な発掘は19世紀になってから、アンジェロ・レメーディ侯爵や建築家カルロ・プロミスといった人物によって行われ、後述するような遺構の一部が姿を現すとともに、彫像、石碑、テラコッタの建築装飾、古銭などが回収された。これらはトリーノ、フィレンツェ、ボローニャ、ラ・スペーツィアの考古学博物館などに初め分散して収蔵されたが、第2次大戦後の1964年、ルーニの遺跡内に博物館が設置されて大部分がここに移された。
ミラーノ大学チームが中心となって近代科学的な基準と方法による発掘調査が始まるのは、ようやく1970年代になってからである。ポンペイ、エルコラーノなどに比べ、いかにヨーロッパの学会のルーニに対する関心が低かったかといえるだろう。この事業はいまも平常的に続いているが、現在は遺跡の一部と博物館が一般公開されるにいたっている。
蘇る理想都市の光芒
さて1世紀に完成したルーニの市域は、不定形の曲線の市壁で囲まれる求心的なプランではなく、長辺(南北)560メートル、短辺(東西)440メートルの直線の城壁で囲まれた矩形をなしているのが珍しい。(軸線は少し右に傾いている。)ただし南東の角だけは河口に接していたため、ちぎり取られたような形となっている(図8)。市域の面積は約24ヘクタール。ポンペイの三分の一ほどだから規模は小さい方だ。最初に述べた5,000人ぐらいという人口の推定はこの面積から計算されたのだろう。城外には二個所の地下墓地と、闘技場がある。ただし市壁は中世に完全に崩壊しており、近年の調査によって基礎部分が確認されたものである。
都市計画はローマの基本理念に基づいて、ここでもやはり南北を通るカルドゥスcardusと東西に走るデクマヌスdecumanusの直交する道路を軸として整然と区画されている。しかもルーニのデクマヌスはアウレリア街道をそのまま取り込んだものである。(現在の国道1号線は遺跡を回避して東の外側を通過する)。二本の主軸道路が交叉する地点がまさにこの都市の政治・宗教の心臓部をなし、すなわちその南側に公衆の集会や商業の場である公共広場フォールムがある。広場は長辺80m、短辺37mの完全に幾何学的な長方形で、東西両側には柱廊がついていた(図9)。注目すべきは広場と柱廊の部分全体が白大理石の舗石で覆われていたことである。ルーニではその他の地区でもいたるところに地元の白大理石を敷き詰めた場所があって、なんと豪奢な舗道を人々は日々行き来していたのだろう。ちなみにローマのあのフォーロ・ロマーノでさえ、石畳はくすんだ凝灰岩や砂岩などだったのである。
一方フォールムに接したデクマヌスの北側にはカピトリウムが建っていたと考えられる。つまりローマ三神(ユピテル、ユノ、ミネルワ)に捧げたこの神殿が、ローマとの絆を象徴する欠くべからざる聖所としてこの都市の最重要の拠点にいち早く建立されたのである。現在、礎石(30.5×20m)が発見されていて(図10)、建物の高さについての推論がなされている。当初の建築は落雷で破壊されたらしく、1世紀の中頃に再建されたが、その際造り直されたイオニア式列柱にもすべてカッラーラの大理石が使われたことが確認されている。それにしてもアウレリア街道から直接城内に入り、いきなりルーニの中心部に出た旅人たちは、この町の思いもよらぬまばゆさを見て絶句するほどの感動を覚えないものはいなかっただろう。
その他の遺構について簡単に述べておくと、まず市域の北東の隅に当るところにGran Tempio(大寺院)と暫定的に呼ばれている神殿の跡があり、これは植民市創立の直後にできた最も古い神殿で、はじめは木造だったと考えられ、エトルリアでよく見られるようなテラコッタの装飾部品が発見されている。これがローマ三神を奉ったものではないかとも考えられたのだが、カピトリウムが建設された後の2世紀中葉になっても石材で改修されたりして存続しているので、同種の神殿が二つあることはあり得ないことから、奉られた神の特定に至っていないのが現状である。
他の古代ローマ都市におけるのと同じく、ここでもいくつかの個人住宅(ドムスdomus)の遺構が発掘されている。ひときわ豪壮なのが「フレスコの家」(Casa degli affreschi)と呼ばれるもので、フォールムの南端に接し、前1世紀から4世紀中頃まで存続していたから相当な有力者の家だったに違いない。敷地が1,300平方メートルもあり、2階建てで大小の庭と「夏の食堂」「冬の食堂」などを備えていた。ポンペイのように屋根まで残っているわけではないが、壁の部分だったと思われる相当数のフレスコの断片(図11)が発見されている。装飾的モチーフが多く、いわゆる第三様式に類する静物画的描写も見られるが、ポンペイなどに比べて美術史的価値はあまりない。それよりも注目すべきは、住居内の各所の床にさまざまなデザインのモザイク装飾が現存しており、特にオプス・セクティレopus sectile(図12)と呼ばれる角形パターンの石を組み合わせる手法では、カッラーラの大理石のほか、冒頭で述べたギリシア産の赤大理石や、エジプトのヌミディアの黄色の大理石など、外国産の石がふんだんに用いられていることだ。つまりルーニの港は地元産の石材の輸出のみならず、地中海各地からの輸入も行い、それらをガリア方面に運ぶなどの集散地の役割を果たしていたことがうかがえるのである。
一方カピトリウムの裏側に「モザイクの家」(Casa dei mosaici)というドムスがあり、ここでは床に表わされた「ヘラクレス」(図13)、「四季の寓意」などの古典的主題がみどころになっているが、色彩的にはもはや輝きを失っている。ただ専門的にはおそらくチュニジアのモザイク職人の仕事であろうとみなされ、港町特有の人的交流の広さが垣間見える。
なお市内の各所から白大理石の彫刻が発見されたことは前に触れたが、その多くは帝政期の皇帝や一族の肖像であり、アグリッパ(図14)、ゲルマニクス(図15)などが、遺跡の一角にある国立考古学博物館に展示されている。数あるローマの肖像彫刻として特記するほどのものではないが、ルーニとローマの親近関係をあらためて証言するものであろう。
城内の北東の隅にはローマ都市に不可欠の劇場の跡があるが、立体的な遺構は全くなく、半円形の座席部分の痕跡を遺すのみなので省略して、東側の市外250メートルほどの平原の中にある闘技場(2世紀)(図16)に触れておこう。長軸88.50、短軸70.20メートルの楕円形のプランで、ここだけは周囲の座席部分がかなりの高さまで残っており、通路部分にはアーチ形の屋根も見えるが、これはさすがに大理石ではなく、砂利や砕石をセメント状に固めた素材でできている。ただ座席は6,000人分あったと推定され、この広さは、もちろんローマのコロッセオに及ぶべくもないが、ルーニの人口規模からすれば大き過ぎると思われるだろう。これについては、劇場で上演される演劇が知識人層を対象としたのに対して、闘技場のスペクタクルは極めて大衆的な娯楽であり、市民のみならず、近隣の集落の農民なども動員したのであろうという興味深い指摘がある。
さてカッラーラの大理石はいまでも盛んに掘られ、世界中に輸出されている。ルーニの港が消滅した後、18世紀にようやく最寄のマリーナ・ディ・カッラーラに港湾が整備され、そこから出荷されるようになった(図17)。しかし日本向けの輸出などは、一旦ジェーノヴァまで運ばれてから大型船に積み替えられて、名古屋港などに向かうらしい。
*ルーニの発掘はまだ進行中であり、参考文献は極めて少なく、本稿の具体的データはluni: Guida Archeologica a cura di Centro Studi Lunensi Ⅲ edizione 1993 によるところが多い。
写真・図面の版権
図1~7:ローマ国立博物館
図8~15:イタリア文化財文化活動省リグーリア州考古学遺産監督局
(Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria)