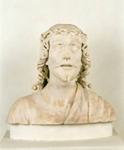蘇生した彫刻家
Matteo Civitali (1436-1502)とは、15世紀後半に活躍したルッカ出身の彫刻家である。と言っても聞いたことがないとおっしゃる方が多いと思う。ひとつには15世紀のトスカーナ地方ではフィレンツェを中心にルネサンス彫刻が花開き、多くの、あまりにも多くの優れた彫刻家が輩出し、それは、フィレンツェのバルジェッロ美術館を訪れてみると一目瞭然、誰でも嫌でも気づかざるを得ない事実である。そのせいでマッテオの名はかなり影の薄い存在になってしまっているからであろう。もうひとつは、どうしても彫刻よりも絵画の方が、彫刻家よりも画家の方が一般的に知られていることが多いせいもあろう。
そもそも1401年、フィレンツェの洗礼堂門扉の公募に多数の美術家が試作品を携えて参加し、結局最後にブルネッレスキとギベルティが残り、最終的にギベルティが勝ちを占めたエピソードはあまりにも有名であり、イタリア美術史の本を繙けば、この事件がルネサンス美術開幕を告げる端緒であったことが分かる。彫刻による幕開けは意味深いことではなかろうか。
今更、どうやら19世紀から20世紀にかけてかなり流行った、ヴァザーリを踏まえた絵画・彫刻優劣論を云々しようとは思わないが、私のように美術入門は奈良の仏像から始まって彫刻に先ず心惹かれた者にとっては、とかく絵画に重点がおかれ、彫刻がどうかすると二義的に扱われるのには常に不満を抱かざるを得ない。実際に初めてイタリアを訪れた者は、古代から始まって、中世、ルネサンス、バロック、さらには新古典主義の各時代を通って現代に至るまでの夥しい彫刻作品に度肝を抜かれるのではないであろうか。
そして、イタリアの大学の美術史の講義を覗いた者は、ここでは、絵画、彫刻、建築、工芸と分けるのではなく、先生によって専門はいろいろ異なるにせよ、また、建築は独自の専門分野で別に扱われることが多いにせよ、むしろ「時代」として捉える傾向が強いということに気づくに違いない。
それでもとうの昔にポープ=ヘネシーが「イタリア彫刻史」(註1)を出しているし、イタリア人著者による「イタリア彫刻史」(註2)も存在するし、単行本に至っては彫刻に関する大小さまざまの著書が出版されているのは周知の事実である。
それにもかかわらず、マッテオ・チヴィターリはイタリアでもあまり知られていない彫刻家であるし、前記の二著にもほんの僅かしか触れられていない。
これはどうやら、ヴァザーリの『美術家列伝』に彼を取り上げた項目がないことが、長い間強い影響を与えてきたように思われる。
しかし、同時にあまりにも多くの優れた彫刻家が続出した15世紀においては、ドナテッロのような傑出した存在から、ヴェッロッキオ、ルーカ・デッラ・ロッビア、ロッセリーノ兄弟、デジデリオ・ダ・セッテイニャーノ、ミーノ・ダ・フィエーゾレ、ベネデット・ダ・マイアーノ、ポッライウォーロなどに至るまで多数の彫刻家が活躍し、フィレンツェのバルジェッロ美術館やドゥオーモ美術館、また市内の教会で彼らの多くの傑作に出会うことができる。中には、あるいは二流作家と決めつけられる者もいるのかもしれないが、彫刻家各人が自己の能力を精一杯に発揮し、それぞれ独自の表現に達しているのを見ると、凄い時代であると感嘆せざるを得ないほどで、マッテオが忘れられても無理もないかもしれないと思わせられる。がその反面、これほどの作家が上記の人々と同等の扱いを受けてこなかったことには不満が残る。そして、後述の作例を見ていただけば、その不満は誰にも納得のいくことと思う。ちなみに、ブルクハルトがマッテオをミーノ・ダ・フィエーゾレくらいの価値ある作家と述べているそうで、今回の特別展の宣伝文句にもその言葉が引用されている。
|
|
|
SPAZIO誌上での既発表エッセー 目次
- 教会巡りの楽しみ(1)
no.53(1996年7月発行)
- 同上(2) グラードを訪ねて
no.54(1996年12月発行)
- 同上(3) カオルレのカンパニーレ
no.55(1997年6月発行)
- マンタ城のフレスコ画について
no.56(1997年12月発行)
- 教会巡りの楽しみ(4) ムラーノ島の教会
no.57(1998年6月発行)
- 同上(5) ロレンツォ・ロットの作品を求めて
no.58(1999年4月発行)
- 同上(6) チヴィダーレ・デル・フリウーリを訪ねて
――ロンゴバルド美術の魅力――
no.60(2001年3月発行)
- 同上(7) ヴェネツィアの好きな教会
no.61(2002年4月発行)
- 同上(8) ヴェネツィアにおけるスクオーラ・グランデ
no.62(2003年4月発行)
- 同上(9) コセンツァのふたつの教会
no.63(2004年4月発行)Web化第一号
|
|
特別展――準備に50年
実は、この原稿を書くきっかけになったのは、ルッカで開かれた特別展「マッテオ・チビターレとその時代」(註3)に負うところが大きい。2004年4月3日—7月11日に開催されたこの特別展は「15世紀後期ルッカの画家、彫刻家および金銀細工師」という副題を持ち、ルッカの国立美術館グイニージ邸で約150点の作品を集めて行われた大規模なものであった。宣伝もかなり華やかだったが、新聞によれば、この展覧会のための準備期間は50年に亘るとのことで、その息の長さにも驚かされる。マッテオの作品が一堂に集められたのは、初めてのことであり、最近の研究の成果によって新たに帰属されたもの、今まで非公開だったものも含まれ、しかも彼の作品のみならず、この場合は主人公が彫刻家であるため、同時代の絵画もかなり展示されているが、彫刻に比べてあまり優れたものは見当たらない。展覧会の主旨は、副題のように当時のルッカの造形文化全体の紹介である。
トスカーナの小都市ルッカは、フィレンツェのずっと西側、斜塔で有名なピサの北東に位置し、ティレニア海にもそう遠くはない。中世に栄えた都市のひとつで、現在でも城壁に囲まれ、町の中心部には中世からルネサンス時代にかけての建物や街並が残る可愛らしい町の一つである。例によって、車での旅行には問題はないが、鉄道やバス利用者にはかなり不便な所で、今回の特別展も、この機会に、美しいルッカの町をもう一度見直そうという宣伝文句で観光客誘致をかなり強く押し出した企画になっている。なお、イタリア彫刻を考えるに当たって、ルッカがピサの近くに位置することも、見逃すことのできない大きな要素である。13世紀から14世紀にかけてピサはトスカーナ地方で最も彫刻が栄えた土地柄であり、ニコラとジョヴァンニ・ピサーノ親子の活躍で頂点に達したが、15世紀に入って政治的にもフィレンツェ支配下に入ると同時に、彫刻の繁栄もフィレンツェに移ってしまったのである。
イタリアでは「誰々とその時代」というタイトルの展覧会は、ほぼ半世紀も前から盛んであり、この種の展覧会では、個々の美術家の作品だけを取り上げる「個展」ではなく、活躍した地方と時代を考慮に入れてグローバルに文化全体を把握しようという傾向が強く、どうかすると美術展というよりも歴史展という性格が強いようなものまで生じてくることになる。
ところで、特別展が行われたのは初めてのこととはいえ、マッテオ・チヴィターリの名はルッカの人々には日常馴染みの名であり、町の中心部にあるプレトリオ(現裁判所)の建物1階のロッジャには彼の立派なブロンズ座像が飾られている。ずっと遅く1893年アルナルド・ファッツィの作である。そもそもプレトリオの建物自体マッテオの設計で、彼の死後息子によって引き継がれたとされており、市内にはマッテオに帰属される建物やその設計、部分的関与などが方々に見られる。
また、1877年にはマッテオの記念メダル(図1)が公開されたり、1875年頃には彼のアトリエの様子が絵に表現されたりもしている(図2)。今回の特別展は、会場に入るとすぐにマッテオの有名な作品の石膏によるコピーの展示から始まり、しばらく先に進めばオリジナル作品に出会えるのであるから、一見奇妙な印象を受ける。しかも、見事なコピーでまるで最近作ったもののように思われるが、実は19世紀末にコピーされたものであり、今や歴史的価値を持つと言えるのであろう。上記のブルクハルトの言葉も考慮に入れると、どうやら19世紀後半にはマッテオの再評価がなされていたように思われて興味深い。
|

(図1)
アドルフォ・ピエローニ、1877年、ルッカ県主催展示会記念メダル、ブロンズ、直径38 mm ルッカ、科学アカデミー、文学・美術部門蔵
▲画像 クリックして拡大

(図2)
ミケーレ・マルクッチ、マッテオ・チヴィターリのアトリエ 1875年? 油絵、190×275cm ルッカ、マンシ邸国立美術館蔵
▲画像 クリックして拡大
|
美しい作品たち
今に残るマッテオの作品はそう数多くはない。展示された作品は、大きく分けて、一連の聖母子像、三体の「受胎告知」のマリア像、キリスト胸像を初めとする聖人像、世俗肖像などになろう。ここでは的を絞って、主としてマッテオの彫刻作品をご紹介することにするが、必ずしも年代順ではない。
まず、この町の最も重要な教会、ドゥオーモ(聖マルティヌスに奉献)の祭壇のひとつには、聖体容器を挟んで左右に跪いて礼拝する天使像(図3)があり、いかにも15世紀の香り立つ瀟洒な作品である。現在この祭壇にある聖体容器は別人の作であるが、マッテオ自身の類似の作品も展示され(図4)、この分野でも彼の力量が優れていたことがよく分かる。
15世紀前半には上記の彫刻家たちによって聖母子像が、丸彫りでも浮き彫りでも数多く制作されたが、マッテオも同じで、ここではまず高浮き彫り作品二点を取り上げよう(図5、6)。図5は背景や装飾部分を金色に塗った大理石作品であり、金色の背景には天使ケルビムの像がふたつ見え、幼児イエスは聖母マリアの膝に直接ではなくクッションに腰を下ろす形で表されている。図6は、背景が異なって花綵で覆われ、イエスは聖母の膝の上に立ち、右手で観る者を祝福している。損傷がひどく、金や青色を塗った跡が辛うじて認められる程度で、大理石自体も摩滅して大変に傷んでいる。これはもともとルッカの街の中のロッジャに何世紀もの間置かれていたためで、ロッジャには屋根があるとはいえ、半ば外に曝されていたせいであり、それだけに市民たちには親しまれていたのであろう。現在は特別展の会場になった美術館の中に大切に保存されている。同時代にフィレンツェのアントニオ・ロッセリーノも同じ素材で類似の作例を残している(図7)。そして、疑いもなく、この図像がルッカおよびその周辺(あるいはトスカーナ全土)に普及したらしく、素材が違うとはいえ、何点ものマッテオ風聖母子像がこの機会に集められた(図8-13)。聖母の膝から少し下までの表現で、膝の上に幼児イエスを抱くこの図像は、互いにあまりにも似ていると思われるであろうが、各像の現在の所在地に気をつけていただくと面白い。イタリアの美術品が国内はもとより、いかにヨーロッパ各地に広まっていったかの一例になろう。
|
 |

|
(図3)
マッテオ・チヴィターリ、礼拝する天使二体 1478-80年頃、大理石、100×71.5×40.2cm(左)、100×72.5×37.5cm(右) ルッカ、ドゥオーモ蔵
▲画像 それぞれクリックして拡大 |
| |

(図4)
マッテオ・チヴィターリ、聖体容器(おそらくルッカのサン・ジョヴァンニおよびサンタ・レパラータ教会にあったもの) 1496年? 大理石、高さ125.7cm ロンドン、ヴィクトリア・アンド・アルバート美術館蔵
▲画像 クリックして拡大
|
| |
 |

|
|
(図5)
マッテオ・チヴィターリ、聖母子像1461-62年頃、大理石に金の彩色、84×57.5×16.5cm プラート、サン・ヴィンチェンツォおよびサンタ・カテリーナ・デ・リッチ修道院、ロザリオのマドンナ礼拝堂蔵
▲画像 クリックして拡大
|
(図6)
マッテオ・チヴィターリ、聖母子像1466-67年頃、大理石に青と金の彩色痕跡あり、73.4×58.6×11.8cm ルッカ、グイニージ邸国立美術館蔵(ルッカの商人ロッジャより)
▲画像 クリックして拡大
|

(図7)
アントニオ・ロッセッリーノ、聖母子像 1460-61年頃、大理石に金の彩色、75×50.5cm ベルリン、国立美術館彫刻部門蔵
▲画像 クリックして拡大
|
|
 |

|
 |
|
(図8)
作家不詳、聖母子像 15世紀60-70年代、彩色と金を塗ったストゥッコ、78×53cm クレフェルト、カイザー・ヴィルヘルム美術館蔵
|
(図9)
作家不詳、聖母子像15世紀60-70年代、彩色と金を塗ったストゥッコ、85.1×55.9cm ロンドン、ヴィクトリア・アンド・アルバート美術館蔵
|
(図10)
作家不詳、聖母子像15世紀後半期、彩色と金を塗ったテラコッタ、61.8×49×14.5cm パリ、ルーヴル美術館彫刻部門蔵
|
| |

|
 |

|
|
(図11)
作家不詳、聖母子像 15世紀後半期、テラコッタ、62×49×15.7cm パリ、ルーヴル美術館彫刻部門蔵
|
(図12)
作家不詳、聖母子像15世紀後半期、彩色と金を塗ったテラコッタ、66×51×14cm スティエンタ(ロヴィーゴ)、アルトーニ=リッツァルド・コレクション蔵
|
(図13)
作家不詳、聖母子像 15世紀後半期、彩色と金を塗ったテラコッタ、65×49.5×16.5cm ミラノ、デ・ドンノ・コレクション蔵
|
|
|
この大理石像からほぼ30年後にマッテオはやや様式の違う聖母子像をテラコッタに彩色して表しており、聖母とイエスの結びつきがずっと親密になり、形の上でもより統一の取れた佳品になっている(図14)。
しかし、マッテオの聖母子像の中で最も有名なのは、「授乳の聖母子」(咳の聖母子)であろう(図15)。これも聖母の膝少し下で切った大理石作品で玉座にだけ金色が塗られている。俗称「咳の聖母子」と呼ばれているのは、民間信仰で、いつの頃からか咳に悩む人はこの像に祈れば奇跡的に治ると伝えられたためであり、信仰の対象として生きてきたわけである。この堂々たる風格のある聖母の作風は、図5や図6の聖母子像がどちらかと言えばフィレンツェ様式に忠実に従っているのに比べ、個性の強い、むしろほかに類例のない不思議な作例になっている。ただし、聖母の右手のほっそりした気品のある指は図5の聖母のものとまったく同じである。授乳の聖母子という図像そのものは、別に新しいものではなく、15世紀前半にもトスカーナやウンブリア地方で時に絵画や彫刻で表現されている。カタログには参照例としてフランクフルトにあるファン・アイク作のその名も「ルッカの聖母子」が挙げられている。
マッテオは、マリアの全身像による聖母子像も創作しており(図16)、次の世紀初頭にそれに倣った作例も見られる(図17、18)。
次に挙げるのは三体の「告知を受ける聖処女」である(図19、20、21)。天使ガブリエルから受胎告知を受けるマリアだけを木彫りに彩色して表している。この図像は13世紀トスカーナ地方に数多く、木彫りに彩色して表現されたもので、伝統に忠実な作例である。ピサやその周辺に残る他の作家の作例には天使も表される場合も見られるが、この三体には告知の天使の姿がなく、この場合は天使像が紛失したわけではなく、おそらく初めから独立してマリアだけを表現したもので、聖母信仰に基づいてマリアの生涯の最も重要な事件の一つを、告知を受けた瞬間に捉えたものであろう。八頭身でウエストから足までがすらりと気品良く長いのは、14世紀から15世紀前半のどの「告知を受ける聖処女」にも見られる特色であり、人を惹きつけてやまないが、実は、信仰の対象としては、これに本物の衣装を着せ、頭にもおそらく飾りをつけていたのである。今思うと不思議な気もするが、現在でもどうかすると聖母の像に白い花嫁の衣装を着せることもあるし、特に幼児キリスト像に豪華な衣装を着せ、装飾品で覆って信者たちがそれに祈りを捧げている光景を見かけることがある。この場合、彫像そのものは人形と同じで、彫刻作品としての価値は問題にならないほどひどい例が多い。ある意味では、現代人がこれらの像から衣装をはぎ取ってしまい、歴史的な彫刻として賞賛するのを当時の人、あるいは作者が見たらずいぶん驚くのかもしれない。図19の解説には、20世紀の初めに、この像が19世紀の衣装を着せられ、まるで「マネキンのようであった」(註4)とある。ともあれ、三体とも20世紀になってから再発見され、修復されたが、マッテオの作とされたのは前世紀半ばとかなり新しい。
次に本格的な裸体像に目を留めてみよう。聖セバスチャンの像である。かなり作風の違うものを二体取り上げてみた(図22、23)。ともにテラコッタに彩色した作例である。聖セバスチャンは古代ローマ時代の兵士だった人で、キリスト教が禁止されていた時代に信者となり、木に縛り付けられて矢で射殺されて殉教したというエピソードはあまりにも有名である。美術史上の図像として面白いのは、いつも若い美青年に表現されていることで、実際は中年の人だったという説もある。裸体表現は異教神話の人物に限られていた時代、美術家にとっては遠慮なく男性裸体像を表現できたほとんど唯一の人物であり、絵画、彫刻に盛んに取り上げられた図像である。ここではまだ14世紀の影響が濃く、16世紀以降の筋骨隆々とした表現に比べればおとなしいが、美青年であることに変わりはない。19世紀に描かれたマッテオのアトリエ(図2参照)には奥の方に、どうやら大理石像らしき聖セバスチャンが見え、この二作例とは違うことが分かるが、おそらく何体も造られたのであろう。そして、絵の中に取り入れられているところを見ると、マッテオ作のこの聖人像がかなりもてはやされていたのではないかと想像される。
|
 |

|
|
(図14)
マッテオ・チヴィターリ、聖母子像 1495年頃、彩色したテラコッタ、91×59×22cm ルッカ、グイニージ邸国立美術館蔵 (ベルナルディーニ広場の祈祷用ニッチより)
▲画像 クリックして拡大
|
(図15)
マッテオ・チヴィターリ、授乳の聖母子(咳の聖母子) 1482-85年頃、大理石に金の彩色、86×77×29.3cm ルッカ、聖三位一体教会蔵
▲画像 クリックして拡大
|
| |

(図16)
マッテオ・チヴィターリ、聖母子像1480-90年頃、彩色したテラコッタ、163×55×25cm カパンノーリ、グラニャーノ、ベルヴェデーレの聖所蔵
▲画像 クリックして拡大
|

|

|
| |
|
(図17)
ヴィンチェンツォ・チヴィターリ、聖母子像 1511-15年頃、彩色と金を塗った木造、132×37×23cm カスティリオーネ・ディ・ガルファニャーナ、使徒サン・ピエトロ教会蔵
▲画像 クリックして拡大
|
(図18)
マッセオ・チヴィターリ(ヴィンチェンツォ・チヴィターリ彩色)、 聖母子像 1514-19年、彩色と金を塗った木造、134cm ヴィッラ・コッレマンディーナ、サン・シストおよびサンタ・マルゲリータ教会蔵
▲画像 クリックして拡大
|
| |

(図19)
マッテオ・チヴィターリ、告知を受ける聖処女 1470年代末、彩色した木造、165×49×42cm ルッカ、ムニャーノ、サン・ミケーレ教会蔵
|

(図20)
マッテオ・チヴィターリ、告知を受ける聖処女 1490年代初、彩色した木造、160×46×22cm ルッカ、サンタ・マリア・デイ・セルヴィ教会蔵
| ※ | 当エッセーのタイトルの右図は、この聖処女像の横顔です(編集) |
|

(図21)
マッテオ・チヴィターリ、告知を受ける聖処女 1490年代末、彩色した木造、163×49×48cm ルッカ、サン・フレディアーノ教会蔵
▲画像 それぞれクリックして拡大
|
| |
 |

|
|
(図22)
マッテオ・チヴィターリ、聖セバスチャン
1492年頃、彩色したテラコッタ、182×55×25cm ルッカ、モンテ・サン・クイリコ、サン・クイリコ教会蔵
▲画像 クリックして拡大
|
(図23)
マッテオ・チヴィターリ、聖セバスチャン
1490-95年、彩色したテラコッタ、65.3×17.7×9.7cm ワシントン、ナショナルギャラリー、クレス・コレクション蔵
▲画像 クリックして拡大
|
|
|
聖人像としては「聖レオナルド像」も挙げられ、マッテオの傑作の一つである(図24)。これもテラコッタに彩色した作品で、150センチとほぼ等身大の実に見事な堂々たる作例である。彫刻鑑賞で困るのは、写真の場合一面しか見られないことであり、ミケランジェロのような傑出した作家の場合は、彫像のあらゆる角度からの写真が撮られ、ある程度の再構成が可能であるが、普通の彫刻家の場合は滅多に行われない。この場合も横顔が実に美しく、カタログの表紙にも使われているほどで、しかも顔の輪郭や表現が先に挙げた「告知を受ける聖母」像にかなりよく似ているのが興味深い。
この他に宗教作品としては、「茨の冠をつけた救世主キリスト」の大理石の丸彫り胸像(図25)や大理石高浮き彫りの「信仰の比喩像」(図26)も展示され、マッテオの多方面にわたる活躍ぶりが偲ばれる。さらに、ここでは1例を挙げるに留めるが、画家との共同作品もある。つまり多翼祭壇画の頂上部分(図27)であるが、「受胎告知」のテンペラ画はバルダッサーレ・ディ・ビアージョという画家が描き、小建築部分というか木工職人的作品というか、他の木の部分はマッテオの作である。14、5世紀のイタリアには木工細工専門だけの職人もいたが、彫刻家の場合は建築家をも兼ねたり、教会のさまざまな聖体容器や聖具のような手工芸的作品も造ったりする美術家は、マッテオのみに限らず多くの人に見られる傾向である。
今までに一瞥したマッテオの作品はすべて宗教作品であったが、15世紀はルネサンスと言ってもまだまだ教会の勢力が強く、したがって作品注文も大部分が教会関係だったろうとは容易に想像がつくが、世俗作品も創作しなかったわけではなく、ここに二作挙げることができる。二作品とも肖像彫刻であり、注文によったものであろうが、モデルが誰であったかは分かっていない。一つは大理石丸彫りで金色の跡も見え、ただ「貴婦人の胸像」と呼ばれている(図28)。気品高い女性の像で、衣服の模様も美しい。もう一つは大理石の高浮き彫りで、これも単に「貴婦人の横顔」(図29)とある。どちらの図像も、15世紀フィレンツェを中心に盛んに創作された肖像彫刻の様式に従っている。
最後に参考作品としてミーノ・ダ・フィエーゾレの三作品を挙げておこう。三点とも今回の特別展に展示されたものであり、三作とも女性肖像彫刻である。
最初に挙げるのは、かつて彩色されていたテラコッタ像で、少女の胸像(図30)である。色は時代とともにはげ落ちてしまったが、初々しい少女像が実にすっきりと表現されている。あと二点は大理石高浮き彫り胸像で、ともに古代ローマ時代の女性の美しい表現で、一つは正に「ローマ皇后の理想的横顔」(図31)と名づけられ、彫刻の台にドンナ・ラウラと書き込んであるが、ラウラという名前は実に多いので、どのラウラなのか同定できないのであろう。理想像と言っても納得できるほどに理想的な美しさをたたえ、香り立つような佳品である。もう一つの方は、かつては部分的に金色が塗られていたらしいが、現在はほとんど残っていない(図32)。ここには聖ヘレナの名が彫り込まれ、コンスタンティヌスの母親で、ごく早い時期にキリスト教徒になった聖ヘレナを表しているのは明らかであるが、彼女をモデルにした肖像ではないので、やはりほぼ理想像と言えるように思われる。このミーノの三作を前述のマッテオの肖像彫刻と見比べてみると興味深い。技法的には、マッテオの作品もミーノの作品に遜色はないことがよく分かる。ただ、理想像と肖像とは違うとはいえ、マッテオの作品にはどことなく地方色が漂うように思われるのである。
|

|

|
|
(図24)
マッテオ・チヴィターリ、聖レオナルド1497年、彩色したテラコッタ、150cm カパンノーリ、ランマーリ、サン・ヤコポ教会蔵
▲画像 それぞれクリックして拡大
|
| |
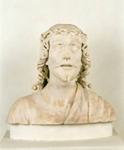
(図25)
マッテオ・チヴィターリ、茨の冠をつけた救世主キリスト 1475年頃、大理石、32×44×22cm ルッカ、グイニージ邸国立美術館蔵
▲画像 クリックして拡大
|

(図26)
マッテオ・チヴィターリ、信仰の比喩像1470-80年頃、大理石、104×60.7×15.7cm フィレンツェ、国立バルジェッロ美術館蔵
▲画像 クリックして拡大
|
 |

|
(図27)
マッテオ・チヴィターリおよびバルダッサーレ・ディ・ビアージョ、受胎告知の天使(左)と聖母(右)(多翼祭壇画の頂上部分) 1469年、木にテンペラ、71×40cm キプロス、個人蔵
▲画像
それぞれクリックして拡大 |
| |
 |

|
|
(図28)
マッテオ・チヴィターリ、貴婦人の胸像 1465年頃、金色の痕跡のある大理石、54.5×49×20.5cm(奥行き最大26.5cm) ピサ、ピサの首位権管理部蔵
▲画像 クリックして拡大
|
(図29)
マッテオ・チヴィターリ、貴婦人の横顔 1490-95年頃、大理石、57×43×10.2cm フィレンツェ、国立バルジェッロ美術館蔵
▲画像 クリックして拡大
|
| |

|

|

|
| (図30) |
(図31) |
(図32) |
|
(図30)
ミーノ・ダ・フィエーゾレ、少女の胸像 1458-63年頃、以前は彩色してあったテラコッタ、31.7×25.4×20.3cm ニューヨーク、マイケル・ホール・コレクション蔵
(図31)
ミーノ・ダ・フィエーゾレ、古代ローマの皇后の理想的横顔 1465年頃、大理石、40.2×30.8×6.5cm トリエステ、市立図書館、ペトラルカ=ピッコローミニ・コレクション蔵
(図32)
ミーノ・ダ・フィエーゾレ、皇后聖ヘレナ 1465-70年頃、部分的に金を塗られていた大理石、46.1×37.2×8.3cm アヴィニヨン、カルヴェ美術館蔵
▲画像 それぞれクリックして拡大
|
|
|
| 註 |
(1) |
John Pope-Hennessy, An Introduction to Italian Sculpture,Part I, Italian Gothic Sculpture, Part II, Italian Renaissance Sculpture, Part III, Italian Mannerist and Baroque Sculpture (3 vols.), London, 1955-63
|
| (2) |
Scultura italiana, 5 vols., Milano, 1966-68
- Rossana Bossaglia, Dall’alto medioevo all’età romanica
- Enzo Carli, Il Gotico
- Franco Russoli, Il Rinascimento
- Valentino Martinelli, Dal manierismo al rococo
- Carlo Pirovano, Dal neoclassicismo alle correnti contemporanee
|
| (3) |
特別展カタログ
AA.VV., Matteo Civitali e il suo tempo – Pittori, scultori e orafi a Lucca nel tardo Quattrocento, Milano, 2004
|
| (4) |
ibid. p.358 |
図版はすべて特別展の主催者、ルッカ市およびルッカ信託銀行基金の提供によるCDより選んだもので、ここに記して深く感謝致します。
I miei più profondi ringraziamenti vanno al Comune di Lucca e alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca per aver gentilmente messo a mia disposizione un CD contenente le immagini delle opere esposte alla mostra.
|