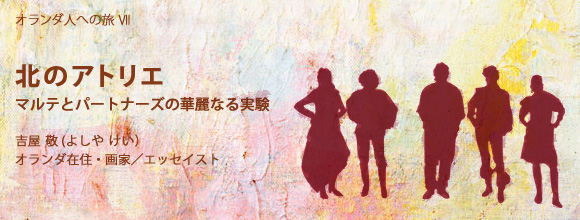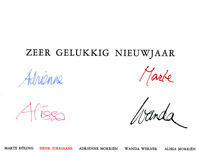第二部
6. ヘンクをめぐる四人の女たち
よく私たちは安易に「運命的な出会い」という言葉を口にする。当人のフィーリングと客観性とが一致していないような、身勝手で滑稽な思い込みの場合も多いが、マルテとヘンクの出会いは文字通り「運命的」と呼んでも差しつかえないドラマを持っていた。
痩せて背が高く、若い美女のマルテにはボーイフレンドは沢山いた。1970年ころにすでに有名な画家だった30歳のマルテは、ある日パーティでヘンクに出会った。29歳のヘンクは精神科医、精神療法医で、当時は大学の恩師のもとで働いていて、その教授の娘と結婚していた。「一目惚れ」とマルテは表現したが、会った瞬間にマルテは自分の人生を共有できるのはヘンクしかいない、と本能的に感じたのだという。躊躇はなかった。マルテは自身の同棲生活にもけりをつけて、ヘンクに積極的にアタックした。ヘンクは3ヶ月後には妻と離婚してマルテと同棲するようになる。
ヘンク・ユリアーンス(Henk Jurriaans)については、1970年代から今に至るまで実にさまざまなゴシップ記事が書かれている。私が調べた資料では、アムステルダムの街中を坊主頭(当時は珍しかったし、奇異でファナティックなマイナスイメージを与えた)で太い葉巻を咥え、奇矯な服装や言動で歩き回る奇人、変人というもの。また1974年に、アムステルダムの市立美術館で25日間、毎日1時間ずつ「生きた彫刻」として全裸で立ち続け、世界的ニュースとなったという記事。また1990年末ころのある有力新聞のアンケートで、「過去で最低・最悪のオランダ人」にノミネートされたことなど、どれをとっても友好的に書かれた記事はあまり出てこない。私はディーターの城で一回会って会話を交わしただけだが、特に奇人・変人という印象は受けていない。とにかくマルテと同棲し始めてからこうしたゴシップの数々を世に残したあと、彼は1990年以降、メディアの表面から姿を消してマルテのアドバイザー、共同制作者として技術面で活躍するようになる。メディアの表面に出てくるのはいつもマルテだが、マルテがヘンクと出会って以来精力的に生み出した数々のモニュメンタルで巨大な作品は、ヘンクの技術的な知識と協力なくしては生み出すことは難しかったに違いない(図39)。
ヘンクとの同居生活が10年目を迎えた1980年ころ、二人にとっては以前からの共通の友人だった34歳の美貌のジャーナリスト、アリッサ・モリエンがヘンクとの恋愛関係に陥った。それから半年と経たない頃、今度はアリッサの妹で30歳の画家のアドリエンヌ・モリエンにもヘンクとの恋愛関係が生じている(図40)。なぜそのような関係になったのか、立ち入ったことはインタビューでも明らかにされなかったが、ではそれが原因でマルテとヘンクの関係に亀裂が生じたのかというと、そうではない。この間の事情は、余人には考えられない何か大きなファクターが全員の上に働いていたと考える以外はないようだ。ヘンクはおそらく非常に優しい心の男性で、女性たちの琴線に訴えかける特別なものを持っていたに違いない。そして何よりも、多くの女性たちを愛したい本能に加えて、双方がお互いを必要としていたのだろう。マルテはアリッサとアドリエンヌ姉妹とヘンクの男女関係を全て知っていたし、ヘンクとの間には何の隠し事も秘密もなかった。
こうして普通の常識から見れば理解に苦しむ、3人の女と一人の男との共同生活が始まった。そこに32歳のグラフィックデザイナーのワンダ・ウェルナーが加わったのは、もう少し後の1983年のことだった。このかなり珍しい男一人に女4人の共同生活は、ほとんどのオランダ人が知るところとなり、このことでマルテの知名度と芸術性はかえって評価が上がったようにさえ思える(図41)。
オランダにはもう一人のアーティストで、アントン・ヘイブルという名前の男の版画家がいた。彼もマルテのグループと同じように、4人の女たちと共同生活をして世間の耳目を集めていた。違うのはアントンのグループは、一人の男を中心として4人の女が集まり、マルテのグループは、マルテを中心として一人の男と3人の女が集まって共同生活をしていることだ。どちらのグループでも、単なる男女関係以外にそれぞれの役割分担があって、共同体が成り立っていたことと、全員が共同体生活の形態に満足していた点が共通している。しかし、世間の通念からすれば、アントンの一夫多妻はイスラム社会や古い日本社会でも見られた現象で、特に珍しいとは言えない。マルテのケースが珍しいのは、グループの中心がヘンクではなく女性のマルテであることだ。ヘンクと女たちは、マルテも含めて男女関係を離れると、アートという円環でマルテを中心に結ばれる共同体なのだ(図42)。
7. VIVA ヘンク!!
古いインタビュー記事で、マルテはこの5角関係について、
マルテ: マルテ他: マルテ:
ヘンクが突然病を得て、短期間の療養の後で他界したのは2005年、68歳の時のことだった。病名は私にはよく理解できなかったが、メラニン色素が関係する一種の皮膚癌のようなものだと理解した。4人の女たちの嘆きはとてつもなく大きかった。マルテはヘンクの死後、もともとはヘンクとの関係からやってきた女たち3人に、ここに留まるも去るも自由にするようにと伝えた。しかし3人ともここを去ることなど全く考えていなかった。ではヘンク亡き後の女たち4人(今はフースをいれて5人)だけの関係はどういうものなのか、あるいは今後どうなるのか? という私の質問に対して、マルテはこう答えた。 私たちはキッチンの横の廊下を通って、厩舎を改造した巨大なアトリエに行った(図47)。かつての農家は母屋につなげて牛馬用の厩舎を持っていたが、このあたりの農家の規模が大きいので厩舎の大きさも並外れている。まずはその天井の高さに驚かされたが、天辺のとんがり屋根の吹き抜け部分は10メートル近くもあるだろうか。工場といった方がいい大きさだ。20m幅くらいの正面の壁には、制作中と思われるマルテの花を描いた大作画面が屏風のような連作形式で掛っている。その先の広い空間の3方の壁全体を埋め尽くして、50点描いたとマルテが言ったヘンクの大きな肖像画がびっしりと掛けられていた。マルテは未発表のこれらの作品は今日は撮影しないでほしい、とカメラマンのわが相棒に言った。ヘンクは正面、横、斜め横といくつかの角度で違った色や背景、手法で描かれていたが、総じて明るく華やかだ。キャンバスはだいたい同じサイズなので隣り同士がぴったりとくっつき、壁面全体が50点のヘンクの巨大な顔で埋められていて壮観だ。
私はゴッホのことをまた思い出した。 アートは確かに個々の作家の孤独と孤立の産物かもしれない。しかし、そこに常に社会への何がしかのメッセージやアンティテーゼが籠められていなければ、アートは単なる個人の遊びや趣味で終わってしまう。同時代のアーティストたちが、お互いの暗黙の了解と共感のうちに、作品を通して社会に投げかけたそうした思想性と試みとが、後世になって、その時代のスタイルや傾向と呼ばれるものになっていく。そしてマルテはそれを一芸術家の孤独な作業としてではなく、パートナーズと一緒に協力して、公共性のある仕事に凝縮させるという大きな試みに挑んでいる。その意味では16、7世紀のオランダに見られた大画家の工房に似ている。しかし巨匠の下で弟子たちが下働きをしていたのと違って、マルテのアトリエでは全員がイコールの民主的な関係でつながっている。またゴッホが望んでいたのは画家共同体であって、17世紀的な徒弟関係ではもちろんないし、マルテのような共同制作ともニュアンスが違うかもしれない。しかし、彼女たちの試みがこのオランダでなされていることは、私には決して偶然には思えない。飛びぬけた理性と知性、気宇壮大な挑戦性と進取の気性、寛容の精神、謙遜さ、そうしたかつてこの国にあったオランダ人の特質を、私はマルテとヘンクを中心としたコミュニティが、現代にふたたび蘇らせたような気がするのだ(図52)。
「私は嫉妬し合う醜い人間の姿を沢山見てきました。嫉妬は自分自身をダメにするだけで何もクリエイティヴなものを創り出しません」
と答えている。
そう、全くその通りで理論的には正しい。多くの人たちがそう思っている。しかし・・・と私は思う。そう伝えた私の問いに対して、
マルテ:
「ヘンクは私にとっても私たち全員にとっても、かけがえのない存在だったのよ。そして本当にヘンクは特別だった。だから私は彼に〈死ぬことを除いては何をしてもいい〉といつも言ってたわ。ヘンクが先に死ぬのだけは絶対にいやだった」
全員:
「そう、私たち全員にとって、ヘンクはすごく特別な人だったのです」
筆者:
「今夜はマルテ、明日はアリッサと、ヘンクが順番に女性たちを訪問することに対して、本当に皆さんの間に嫉妬や抵抗はなかったのでしょうか?また、何が皆さんに、ヘンクがそんなに特別だと思わせたのですか?」
マルテ:
「ヘンクは心が広く大きかったのよ。そりゃあヘンクにとってだって、4人の女を順番に回って歩くのは、体力的にもかなり大変だったと思うわよ」
と言いながらマルテはおかしそうに笑った。
「でもヘンクと私たちの恋愛関係は、当事者二人だけのことだけど、人間関係という観点から見ると、男女関係とか嫉妬とかを超えていたのよ。そんなことは問題じゃなくて、彼の存在自体が私たちに力を与え、彼は私たち全員が一緒に成長することを教えてくれたのです」
「ヘンクはね、明るくて、そこに彼がいるだけで私たちはハッピーだった。私は今でも、あなたが入ってきたその後ろの入口から、彼がにこにこしながら“ヤア”って入ってくるような気がしてならないの」
アリエンヌ:
「私たちはみんなヘンクが大好きだった。私たちはそれぞれにヘンクとの忘れ難い思い出を持っているけど、ヘンクを巡っての女同志の嫉妬なんて全然考えたことはないわ」
アリッサ:「彼にはすごいユーモアがあって、いつでも冗談ばかり言って私たちみんなを笑わせてくれたわ。ヘンクは信じられないくらい心の広い、おおらかな人でした」
ワンダ:
「ヘンクはいつも公平だったし、全員にとってそれぞれに大切なかけがえのない存在だった」
マルテ:
「あなたが調べ上げたヘンクの記事はみんな悪意に満ちたでたらめよ。ヘンクは、冗談は好きだったけどすごく真面目な人間で、決してプロヴォ(1970年代に流行した反体制運動で、奇矯な服装や行動で社会への不満を表明した)活動をしたわけじゃないのよ。彼が変わった服装をしたのは、単にファッションに興味があっただけ。それと市立美術館で、全裸で立ったというのも嘘よ。彼は着衣で、ある一定区間の中に立って、寄ってくる観客と話をしたりお酒を飲んだりして、美術品の在り方というものに疑問を提示したかっただけなのよ」
「でもヘンクはすごい浪費家だったわね。家族中一番の浪費家だった。彼が買った最高の贅沢品は二機のセスナね。私がすごく飛行機が好きなので、お陰で私たちはそれに何回も乗れてすごく楽しかった!尤も今は処分してしまったけどね。ヘンクはそういう気宇壮大な人だったの」
「私たちが彼の浪費癖を怒る? とんでもないわ。だってヘンクは死ななければ何をしてもいいって、私以外にもみんなが暗黙のうちにそう思っていたんだから」
筆者:
「もし今後ヘンクに代わる男性が現れたら? あるいはその必要性は?」
「新しい恋人が現れるのは別に構わないけど、ヘンクに代わる人は絶対に現れないって断言できます。それに私たちは沢山のことをヘンクから学んだし、沢山の知的財産をヘンクは残してくれたから、今後は彼なしでもやっていけるし」
マルテ:
「私はヘンクの死後、きっと彼を忘れるためなのかしらね、この二年間で50点のヘンクの肖像画を描いたの。これからも描き続けるつもりよ。後でアトリエでお見せするけど、近いうちにこれをどこかでまとめて発表しようと思っているわ」
「ヘンクはもういないけど、私はヘンクがいつもここに座っていると思っている。ヘンクはいつでもどこでも私たちと一緒にいるのよ」(図43)
VIVA ヘンク!! 驚くほどのヘンク礼賛の大合唱である。その上今までの対応とは違って、ヘンクについて語る女性たちの言葉には信じられないような生気と熱気が感じられる。一人の女で満足できなかった男への恨みや批判などは、誰からもどうやっても聞き出すことは無理そうだった。これは単に男女間の恋愛感情だけではない、何か特殊なヘンクへの感情がここには充満しているような気がした。それにしても没後3年、なお4人の女たちにこれほどに愛され慕われるヘンクとは、一体どんな男だったのだろうかと、私は目の前のヘンクの肖像画をあらためて眺めた(図44、図45、図46)。
8. 家族を超えたコミュニティ
「ヘンクを中心に成長してきた私たちは、今はパートナーでもなく単なる仲間でもない、本当の家族以上の家族だと思ってるわ。家族だって夫婦だってうまく行かないケースは沢山あるでしょう。でも私たちは三十年一緒に暮らしお互いをよく知り、尊敬し、独立した個人の集団として一軒の家で共同生活をしている。仕事や家庭の運営、何かあった折にはいつでも一致団結できる固い信頼と絆で結ばれています。これは家族以上の存在であり、同時に一つの企業と言ってもいいと思う。個々の収入はすべてアリッサが管理する口座に振り込まれ、そこから全ての費用が捻出されているのよ。個々の収入の差などは一切問題になりません。お互いがこの家族と企業を支えていくのに何らかの役割を担っているし、誰か一人がいなくても成り立たない存在だからです。買いたいものがあれば個人的に買うのも自由だし、問題が起こったことなど一度もないわ」
「そう、私たちはここを自分の家庭だと思っているし、私たちはみんな家族の一員だと思っています。ここ以外に私たちの家族も家庭も行くところもあり得ないわ」
と3人の女たちが異口同音に言った。一年半前に二人の娘が住むこのコミュニティの
一員となった母親のフースについても、マルテは、
「彼女が私たちにジョインしたことで私たちの家庭と生活がもっと充実し、豊かで楽しくなったわよね?」
と確認するように言って、一同を見まわした。みんながフースを自分の母親のように思って大切にしているのは明らかだ。長時間のインタビューでじっと一緒に座って聞いていたフースは、さすがに少し疲れた様子だった。アリッサが立ってフースの腕をとり、自室に連れて行った。
同じ空間の左手コーナーには、父ヘーラルトの具象的な作品が沢山かかっている。小ぶりなサイズが多いが、当時の家庭に掛けるサイズとしては普通だった。父が描いた美少女マルテの肖像画もあった。魚貝類や日用品などを描いた戦前まで主流だったオーソドックスな静物画が多いのは、彼の生きた時代の反映だろう。
もう少し先の空間は、アドリエンヌの展示室兼アトリエになっていて、彼女の作品が10点ほど掛っていた(図48)。アドリエンヌ自身も絵描きだが、長年ヘンクと一緒にマルテの立体作品の制作にかかわってきた。ヘンクとの制作時に技術的なノウハウを細かく書きとめた二冊のノートを作っていたので、それを基にヘンク亡き今も、マルテの立体作品の制作をアドリエンヌが協力して支えている。制作のコンセプトを考えるのも一緒にすることがあるという。
アドリエンヌの展示室兼アトリエの裏側には、2006年に98歳で他界したマルテの母マルティーヌの作品が20点ほどかけられたギャラリーがあった。もともと母が住んでいたこの農家にマルテたちが引っ越してきたのだという。
それから通路を左に曲がるとまずはアドリエンヌの自室があり、沢山の作品や写真が掛けられている。その隣にワンダの部屋があった(図49)。ワンダは絵描きとして主に平面作品の制作でマルテに協力する時以外は、自作のグラフィック作品に専念している。時々大きな注文作品を描いたり、展覧会を開いたりしている。壁には自作がびっしりと掛けられていた(図50)。
その隣がアリッサの部屋だった。アリッサはかつてジャーナリストでありライターでもあったが、ここで共同生活をするようになってからは実務面はすべて彼女が担当している。出納課長、庶務課長、秘書課長であり、その上料理長もアリッサの兼任だ。日本食の好きなマルテと仲間たちのために、時々アリッサは握り寿司まで作る。全員がアリッサの料理の腕前を称賛したが、写真で見る握り寿司の飾り付けはなかなか本格的で、彼女の美的センスがわかる(図51)。だから、アリッサがいないとこの家は成り立っていかないほどの重要な役割を担っている。
彼女たちの自室は、どの部屋も広々としていてマンションの一軒分くらい、100㎡くらいの大きさがある。全員が自室を思い思いの個性的なインテリアで整えて、独立した快適な暮らしをエンジョイしているのだ。アリッサの部屋を出ると私たちがさっきまでいた共通の居間で、これで一階を一周したことになる。肝心のマルテの居住空間は残念なことに見せてもらえなかった。マルテによると、あまりにも乱雑なので人には見せられないのだそうだ。ヘンクの部屋も見せてはもらえなかったが、今も手をつけないままにしてある。
この家では、全員がマルテを中心としてそれぞれの役割を持ち、共同生活に貢献している。誰ひとりが欠けてもこの共同体は成り立たない。こうした共同生活はヘンクのアイディアだったのかと思って聞いてみると、全く自然発生的に出来上がったものだという。3人の女たちがマルテをコミュニティの主宰者、あるいは家族の長としての敬意をもって接しているのに対して、マルテ自身は全員を立てるよう、それとない細心の心配りで接している姿が新鮮で印象的だった。
9. ゴッホの「南のアトリエ」とマルテの「北のアトリエ」
パリ時代以降、ゴッホは日本の画家たちが一種の共同体を作って共同生活を営んでいるという、どこからか得た多分に誤った情報を基にそう信じ込んでいたふしがある。ゴッホの共同体構想がすでにアルル以前の1883年の段階で、フローニンゲン近郊のドレンテ州で芽生えていたことは第一章で書いた。しかしパリで日本の画家の共同生活のことを知ったゴッホは、アルルでの画家共同体構想の夢をますます膨らませていったのだろう。ゴッホは画家たちが共同生活で刺激し合って優れた作品を生み出すこと、弟のテオが作品を売ることによって、画家たちが安定した生活環境の中で安心して制作に没頭できることを夢見ていた。これがゴッホにとっての「南のアトリエ」の共同体構想だった。
ゴッホ以後の世界では、芸術家たちが共同体構想を夢見ることはだんだんに少なくなっていった。20世紀初めのオランダでは、モンドリアンを中心とした「デ・ステイル」グループが、また戦後はカ―レル・アッペルを中心にした「コブラ」運動などが起こったが、現代ではそうした芸術運動やグループは姿を消してしまった。アーティストたちがかつてのような貧しさにあえぐことが少なくなり、生活が安定し、さまざまな実験芸術が大衆層にも抵抗なく、すんなりと受け入れられるようになったため、芸術家たちはグループを作って既成社会にプロヴォケイトする必要もなくなった。そしてグループに代わって画廊が台頭し、商業美術としての販売プロモーションを促進したことによって、アートの在り方そのものが大きく変化したためもあるだろう。
彼女たち全員が何度も繰り返した、「ヘンクは特別だった。ヘンクは偉大だった。ヘンクは私たちと一緒に生きている」という言葉の真の意味を、私は最初どうしても理解することができなかった。しかし、多分ヘンクに備わっていたに違いないこれらのオランダ人の優れた特質を彼女たちだけはよく理解し、それを愛したのだということをこの稿を書きながらやっと理解できたような気がした。そしてそれはまた、オランダ人・ゴッホにも備わっていた極めてオランダ的な特質でもあったと思う(図53)。
マルテとヘンクとパートナーズたちは、ゴッホがついに成しえなかった「南のアトリエ」の構想をこの地で発酵させ、意図せずに「北のアトリエ」の構築に成功したように思える(図54)。マルテの作品とライフスタイルが、後世の美術史上でどのような評価と地位を得るかは、神のみぞ知るであろう(図55)。
SPAZIO誌上での既発表エッセー 目次