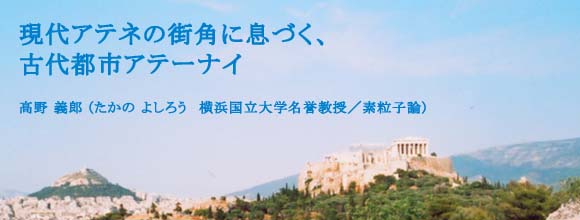〔1〕古代の都市国家アテーナイを散策
| 古代アテーナイおよびその周辺の地図を見る |
哲学の道、ペリパトス 現代ギリシアの首都アテネを訪れた人なら誰も、アクロポリスの丘へ登り、澄み渡った青空の下、壮麗なパルテノーンの神殿を仰ぎ、生きている悦びが体中にこみ上げてくるのを感じたに違いありません。
アクロポリスへの観光客の出入口は西斜面中腹にあって、そこから、遺跡を囲む金網の外側に沿う道を、アクロポリスを右に見て、時計回りに歩いてみましょう。金網の内側にも、崖の真下を巡る道が見えます。これがペリパトスと呼ばれていた古代の道(図1)で、眺めも良く、市民がそぞろ歩きを楽しんだものでした。
このペリパトスという言葉を辞書で引いてみますと、先ず、「そぞろ歩き」、次に、「遊歩道」、そして、もう一つ、「歩きながらの会話、一般には、歩きながらの哲学的な議論」、と記されています。ソークラテースやプラトーンも、子供の頃から、この道を走りまわっていたかもしれません。
辿ってきた外側の現代の道は、しだいに細くなり、曲りくねって、階段になったりしますが、東南斜面、ディオニューソスの劇場の近くまでは、ペリパトスを追うことができます。そこから先、ペリパトスは、劇場の観客席の最上部を抜け、アスクレーピオスの神域を通って、アクロポリスの中腹を一周していました。
クレプシュドラーの泉 このアクロポリスの丘は石灰岩でできていて、山肌には多くの洞窟が見られます。
例えば、西北の角、アテーナーの神域への出入口、プロピュライアに近いところにも洞窟が口を開けていて、ここにはクレプシュドラーの泉がありました。この泉は、すでに新石器時代に知られていて、早くからニュンペー(ニンフ)崇拝の中心になっていたようです。前5世紀には、井戸屋形も設けられ、永く聖なる泉として崇められてきたのでした。
都市国家アテーナイの市庁舎と
そして、このアグラウロスの祠の位置が特定されたことによって、都市国家アテーナイの市庁舎プリュタネイオンの位置も分かってきたのです。というのは、パウサニアースの『ギリシア記』(2世紀後半)には、プリュタネイオンの近くにアグラウロスの祠があると記されているからなのです。
ここ市庁舎には、都市国家アテーナイの炉があって、女神へスティアーに守られ、不断の火が燃えていました。また、ここには、前594年の改革を裏付ける、ソローン(前640年頃~前560年頃)の法の刻文も保管されていたのでした。
それに、パウサニアースによれば、プリュタネイオンはトリポデス(
話はそれますが、近代ギリシアの独立に情熱を燃やした、英詩人バイロンも、リューシクラテースの記念碑の近くに住んでいたことがあるそうです。
名残のイーリッソス さて、ディオニューソスの劇場から、さらに東南の方向へ進めば、ゼウスの神殿があり、そこまでが古代アテーナイの市内で、市壁に囲まれていたのはいうまでもありません。そして、市門を出れば、イーリッソスの清らかな流れがありました。この河のほとりが市民の憩いの場であった様子は、プラトーンの対話篇『パイドロス』に窺うことができます。ソークラテースと友人のパイドロスとは、イーリッソスの清流に足を浸しながら、恋について話し合うのです。
このイーリッソス河は、残念なことに、今はヴァシレオス・コンスタンティヌス大通りへ姿を変えてしまいました。しかし、幸いなことに、ゼウスの神殿の近くだけ、昔のイーリッソス河が遺されていて、しかも、そこには中の島があり、聖域とされていたところなのです。ただ、今は荒れ果てたままになっている(図3)ので、筆者の友人で、アテネ大学のM教授が中心になって、復旧を働き掛けていると聞いています。
女神アルテミスを迎えて この辺り、左岸はアルデーットスの丘で、そこにアルテミスの神殿のあったことは、先に記した『パイドロス』で、ソークラテースも語っていますが、その石垣(図4)が、大通りに沿って、わずかに残っているのも見落とさないようにしましょう。
パウサニアースによれば、デーロス島からやってきた女神アルテミスが、最初に狩をしたのがこの辺りなのだそうです。
パンアテーナイア祭の競技場 また、ソークラテースとパイドロスとの対話の舞台は、数百メートル上流の、競技場スタディオンの前辺りだったと思われます。この競技場は、第1回近代オリンピックの会場として知られていますが、もともとこれは、アテーナイの守護女神アテーナーの祭典、パンアテーナイア祭の競技のため、アルデーットス、アグラー二つの丘の鞍部に、紀元前330年、雄弁家のリュクールゴスによって造られたものでした。
さらに、144年の競技のため、第二次ソフィスト運動の代表的人物、ヘーローデース・アッティコスが、私財を投じ、ペンテリコンの大理石で美しく飾りました。パウサニアースの『ギリシア記』には、「ペンテリコン山の石切場の大半が、この工事のために枯渇してしまった」などと書かれています。
民会会議場の演壇に立って さて、次に、アクロポ
リスの丘の西に向き合う、プニュックスの丘の、なだらかな坂道を登りましょう。頂上は白い石灰岩の広々としたテラスになっていて、アテーナイ民主制の最高決議機関、民会は、前6世紀末からは、ここで開かれたのでした。
議場は、扇形に、北北東へ広がり、その
この演壇に立ってみますと、前方右手遥かにパルテノーン神殿が望まれます(図6)。アテーナイの政治家たちは、6,000人を超える市民たちを前に、そして、都市国家アテーナイの守護女神アテーナーに見守られ、その責任の重さをひしひしと感じたに違いありません。
市民生活の中心、アゴラー その次には、アクロポリスの丘の西北の麓、アゴラーを訪ねましょう。アゴラーは、もとは集会を意味する言葉でしたが、しだいに集会の場所を指すようになり、集会も初めは主に公的なものだったでしょうが、後には市民がさまざまな用事で集まってくる場所、情報や意見の取り交わされるところになりました(図7)。それにつれて、市場と訳されるように、経済的な機能も備わってきます。アゴラーこそ、市民生活の中心であり、民主政治を支える場であったといえましょう。
アクロポリスの西北部、ペリパトスから分かれて、アゴラーへ降る道は、古代、パンアテーナイア祭の行列が登ってきた道でした。このパンアテーナイア祭の道は、アテーナイの西北の門、ディピュロン門の辺りから出て、アゴラーを西北から東南へ斜めに通っていました。
ソークラテースの産婆術 アゴラーでは、ソークラテース(前470年~前399年)ゆかりのところを巡るのもよいでしょう。弟子のクセノポーンやプラトーンによれば、ソークラテースは、ゼウスのストアー(柱廊、前5世紀)によく姿を見せたようです。このストアーの跡は、西北の端の方にあって、いささかさびれた感じがするのは惜しまれます。
ソークラテースは容貌魁偉、それに、何時も裸足で、アゴラーや公共体育場など、市民の多く集まるところへよく現われました。そして、これといった若者を見付けると、彼との問答を楽しみながら、深い思索へと導きました。
その代表的な対話は、「ソークラテースの産婆術」でしょう。ソークラテースのお母さんは当時有名な産婆さん(助産婦)でした。自分も産婆なのだ、知識の産婆なのだ、とソークラテースは言います。産婆は、妊婦に子供を与えるのではなくて、妊婦が子供を産み易いように助けるのだ。同じように、知識も与えられるものではなく、自分自身で産み出さなければならないものなのだ。私は決して知識を与えるのではなく、話し合うことによって、知識の産み出されるのを助けるのだ。私は知識の産婆なのだ。
ソークラテースの産婆術こそが、学び、教えることの、基本ではないでしょうか。
ちなみに、このソークラテースの産婆術は、プラトーンの対話篇『テアイテートス』に出ています。対話の相手のテアイテートスは、後に優れた幾何学者になった人物であろうと思われます。そして、その場所は、後に触れますが、リュケイオンの公共体育場だったようです。
評議会議事堂とトロス ゼウスのストアーの南には、評議会議事堂ブーレウテーリオン(前6世紀~前5世紀)、そして、トロス(前465年頃)と呼はれる円形の建物、アテーナイの行政の中心がありました。 ブーレウテーリオンの東には、排水溝を越えて、公共掲示板(前4世紀)が設けられていたことも記しておかなければならないでしょう。
ソークラテースが、前399年、毒杯を仰いだ牢獄は、トロスの西南100メートルばかりのところにありました。裁判は、トロスの東南50メートルほどのところにあった建物で行われたようです。
へーパイストスの神殿 ゼウスのストアーやブーレウテーリオンの背後の丘には、ヘーパイストスの神殿(前5世紀中頃)が聳えています。この神殿は、レームノス島との親善のために建てられ、それぞれの守護神、鍛冶の神、火の神ヘーパイストスと学芸の女神アテーナーとのブロンズ像が、合わせ祀られていました。
近頃は、先史時代の遺跡の発掘も進み、神話に残る母系制時代の痕跡も論じられるようになりました。例えば、あの勇猛な英雄ヘーラクレースは、女神ヘーラーのパートナーであったと推測されています。また、女神アテーナーのパートナーは、鍛冶の神ヘーパイストスであったと推測されているのです。上に述べたヘーパイストスとアテーナーとの合祀にも、何か因縁めいたものが感じられるではありませんか。
なお、レームノス島のへーパイストスの神殿(図8)にも詣でましたが、神殿中庭の地面が、火の神事が行なわれていたのでしょう、一部分赤く焼けているのはとても印象的でした。
重量、容量の原器 反対側の、東の端を限って、アゴラー博物館があって、ユニークな展示品に接することができます。例えば、古代の重量や容量の原器(前5世紀~)(図9)もあって、これらは先に述べたトロスに保管されていました。法廷弁論の時間を計る水時計や、票決に使うコマのような形のものなど、法廷で用いられた器具類(前5世紀~)も並べられています。
面白いのは、陶片追放に使われた、テミストクレースらの名を彫った、たくさんの陶片(図10)です。これは、民主制を守るため、僭主になるおそれがあると思われる人物の名を陶片に彫って投票し、追放する制度で、前5世紀に行なわれましたが、本来の目的よりも、政争の具に用いられる弊害が大きく、長くは続きませんでした。
演劇も、また、前5世紀の初め、ディオニューソス劇場が造られるまでは、アゴラーで、仮設の劇場で演じられていたのでした。
ストアー学派発祥の地 見落とさないようにしたいのは、ストアー・ポイキレー(彩色柱廊、前5世紀)(図11)です。キュプロス島生まれの哲学者ゼーノーン(前335年~前263年)は、前3世紀前半、ここで講義をしていましたので、ストアー学派と呼ばれるようになりました。ところが、このストアー・ポイキレーは、アゴラーの他の部分から切り離されて、北側の、モナスティラーキーの人込みにまぎれてしまっています。現在のところ、柱廊への階段までは掘り出されているのですが、大部分はまだ民家の下に埋まったままで、発掘はなかなか進まないようです。
ディオゲネース・ラーエルティオスの『ギリシア哲学者列伝』(2世紀末~3世紀初め頃)によれば、ゼーノーンは、無意味なおしゃべりをしている青年に向かってこう言いました。「我々が耳は二つ持っているのに、口を一つしか持たないのは、より多くのことを聞いて、話す方はより少なくするためなのだ」
アッティカの墓碑 アゴラーのさらに西北には、市壁の内外にわたって、ケラメイコスの墓地がありました。日の沈む西の方に冥界をイメージするのは、多くの民族に共通するところでしょう。発掘もかなり進んでいて、古代の墓碑は、国立考古学博物館に収められています。いわゆる《ヘゲソの墓碑》(図12)をはじめ、前4世紀の頃の墓碑には、亡き人の面影を偲ぶ浮彫が施され、とりわけ心打たれるものがあります。ドイツ象徴派の詩人リルケの『ドゥイノの悲歌』第二も引いておきましょう。
- おんみらはアッティカの墓碑に刻まれた
- 人間のたたずまいのつつましさに
- 息をひそめたことはなかったか
- 愛と別れとは私たちの場合とは別のものでできているかのように
- そっとふたりの肩の上におかれているのではないか
- 想いたまえふたりの手を
- からだには力が満ちているのに
- その手には力がこもることなく触れ合っているのを
- 自らを抑えているこの人たちは知っていたのだ
- これが私たちのなしうる限りであることを
- そのようにそっと触れ合うことが
- 私たちのありようであることを
- 人間のたたずまいのつつましさに
- (上原和訳、一部加筆)
ここケラメイコスを通る道は二つあって、南側の「聖なる道」は、「聖なる門」を出て、北寄りに西へ20キロメートル、死と再生の秘儀の場、エレウシースへ向かい、北隣の、ディピュロン門を出た道は、真直ぐ西北へ1.5キロメートル、アカデーメイアの公共体育場ギュムナシオンへ通じていました。
エレウシースの秘儀 エレウシースは、母神デーメーテールと姫神ペルセポネーとの聖域で、エレウシースの秘儀は、農耕祭祀であるとともに、死と再生の秘儀でした。秘儀の場テレステーリオン(前6世紀後半、前5世紀半ば、ローマ時代)(図13)は礎石しか残っていませんが、ハーデスがペルセポネーを連れ去った、冥界へ通う洞窟(図14)、娘を探しあぐねたデーメーテールが腰を下ろして疲れを休めた、カリコロンの井戸(図15)などもあって、とても印象深いところです。
南の奥まったところに博物館も建てられていて、デーメーテール女神像(前420年頃)(図16)やディオニューソス神像(ローマ時代の模刻、原作はプラクシテレース)(図17)、それに、祭具ケルーノス(図18)など、エレウシースならではの、ユニークな展示品を数多く観ることができます。それに、アテネの国立考古学博物館に収められている、いわゆる《エレウシースの浮彫》(前440年~前430年)(図19)や《ニンニオンの額》(前4世紀前半)(図20)も見落とさないようにしましょう。
ケーピーソス河畔の緑地、アカデーメイア アカデーメイアは、前6世紀、ケーピーソス河の治水工事にともなって造成された緑地で、女神アテーナーの聖木オリーヴの並木があり、体育場ばかりではなく、さまざまな神々を祀る
プロメーテウスとヘーパイストとの祭壇も築かれていました。ともに火の神、技術の神で、アテーナイや、広くアッティカ地方の職人たちに崇拝されていました。そして、女神アテーナーの祭典、パンアテーナイア祭の松明競走は、ここをスタート地点として、アゴラーを通り、アクロポリスの東麓にあった、市庁舎プリュタネイオンがゴール地点になっていました。市庁舎には、先に記しましたように、都市国家アテーナイの炉があって、女神ヘスティアーに守られ、不断の火が燃えていたのです。
アカデーメイアで教えたプラトーン プラトーン(前427年~前347年)が、アカデーメイアの公共体育場と、その東北、コローノスの丘に近い自宅とを使って、彼の学校を開いたのは、前387年頃のことでした。公共体育場には、その附属施設として、講義や討論のための部屋エクセドラーが設けられていたのです。体育場は礎石だけしか残っていませんけれども、その間取りを辿ることはできます。ローマ時代初期のものですが、一部古典期のものも利用していて、プラトーンの頃の体育場の様子を窺うことはできましょう(図21)。
「幾何学を知らざる者は入るべからず」、この有名な言葉は、プラトーンの教育方針を端的に表したものでありましょう。
アカデーメイアの学校は、変遷を重ねて、東ローマ皇帝ユスティニアーヌスによって閉鎖されるまで、529年頃まで続きました。そして、永くヨーロッパにおける研究と教育の場の典型と考えられてきたのでした。ルネサンス以後、研究組織や教育機関は、しばしばアカデミーと名付けられていますが、これがプラトーンの学校に由来することはいうまでもありますまい。
アカルナイ門に残る轍の跡 今度は、古代アテーナイの北の門、アカルナイ門の跡です(図22)。それは、オモニア広場から(現代の)市庁舎の方へ行ったところにあって、近代建築の下に、巧みに保存されているのを観ることができます。この辺りは堀も囲らされていたようで、それを越える道は、門へ向かってその幅が次第に狭められていて、防衛上なるほどとうなずけます。それに、地面に残る
風の塔 ここから南へ行けば、アクロポリスの北麓には、ローマ人のアゴラーがあります。その東南偶に建つ《風の塔》(図23)は、前2、あるいは、前1世紀に、アンドロニーコスによって建てられたもので、日時計、水時計、風見の三つの働きをしていました。八角柱の各壁面上部には、それぞれの方向から吹く風の神の浮彫が施されていて、屋根の頂きに付けられていた海神トリートーンの風見が回転し、その杖でこれらの浮彫を指すようになっていたのです。日時計は、正面の、南の壁面に設けられました。水時計の水は、先にも触れました、アクロポリスのクレプシュドラーの泉から引いたといわれています。
ちなみに、クレプシュドラーは水盗人といったような意味ですが、こんなふざけた名前を付けられた、サイフォン式の器具があり、当時の水時計がそれに似た構造をしていたため、水時計自身もクレプシュドラーと呼ばれるようになったのでした。そして、さらに、クレプシュドラーに水を送る泉までが、クレプシュドラーの泉と呼ばれるようになってしまったのでした。
歩きながら教えたアリストテレース 《風の塔》の辺りから、プラーカの雑踏を東の方へ抜ければ、シンダグマ広場も遠くはありません。ここは現代都市アテネの中心といってもよいでしょう。最近開通した地下鉄メトロのシンダグマ駅には、工事で発掘された遺構も展示されています。
紀元前334年、アレクサンドロス大王がペルシア遠征に旅立ったと同じ年、アリストテレース(前384年~前322年)は、リュケイオンの公共体育場――先にソークラテースの産婆術について述べたときに触れました――を利用して、彼の学校を開きました。それは、アテーナイの東の門、ディオカレース門を出てすぐ東南のところでした。それに、学校に寄付された土地がその北に隣接していて、『植物誌』で知られる、弟子のテオプラストス(前370年頃~前286年)が後を継いだ頃には、そこに学芸の神々ムーサイ(ムーサの複数、9柱)を祀る神殿ムーセイオンがあり、図書館などの施設も造られていたと思われます。現在のシンダグマ広場がほぼこの学校の敷地に当たっていて、西北の隅にはその境界石も残されています(図24)。
アリストテレースは、リュケイオンの遊歩道を歩きながら学生たちを教育したので、彼の学問の伝統を継ぐ人々は、逍遥学派ペリパテーティコイと呼ばれました。アクロポリスを巡るあのペリパトスでも、学生たちと議論しながら歩いているアリストテレースを見かけたことでしょう。
ヘレニズム時代、エジプト王国の首都アレクサンドレイアに、プトレマイオス一世によって創設された、学芸の研究施設ムーセイオンは、このアリストテレース、テオプラストスの学校をお手本にしたものでした。
英語のミュージアム博物館は、学芸の神々ムーサイを祀る神殿ムーセイオンがその語源であることはいうまでもないでしょう。
以上、私たちは、よく知られた古代の遺跡、パルテノーン(前447年~前438年)を始めとするアクロポリスの神域、麓のディオニューソス劇場(前5世紀初め)、ゼウスの
神殿(後130年頃)、それに、アテネ国立考古学博物館には深くは立ち入らず、華やかではなくても、街角のところどころに息づき、また、顔を覗かせている、古代のアテーナイを訪ねてきました。
これに続いて、私たちは、アテーナイの近郊、アッティカ(アッティケー)地方へ足をのばすことにしましょう。
ちなみに、古代の都市国家(ポリス)アテーナイは、都市部だけではなく、その領域はアッティカ全土に及んでいました。人口も、最盛期には、約30万人と推定され、例外的に大きいポリスでした。
アテーナイの民主制 ここで、古代都市国家アテーナイの民主制について、その概略を記しておきましょう。
前508年、クレイステネース(前565年頃~前500年)によって創設され、アテーナイ民主制の基礎となった、10部族制は、アッティカ全土を市部、沿岸部、内陸部の三つに分け、それぞれをさらに10に細分して、これら30の区域をトリッテュス(3分の1の意)と呼びました。そして、トリッテュスの内、市部、沿岸部、内陸部に属するものをそれぞれ一つずつ選んで組み合わせ、これを1部族とし、10の部族が創設されたのでした。この組み合わせには、人口をはじめ、職業や階層など、さまざまな観点から、部族間に偏りのないように注意されたことでしょう。
なお、トリッテュスは数個のデーモスからなり、個々の市民は、それぞれのデーモスに登録され、アテーナイの市民として公認されました。
クレイステネースによるこのような改革は、有力な貴族の地盤を分断して、国政の主導権を握らせないようにするものでした。
10部族制に基く制度上の改革として、先ず挙げなければならないのは、1部族50人からなる、500人評議会の設置でしょう。
先にも記しましたように、最高決議機関は、全市民から構成される、民会でした。そして、評議会は、民会に議事を提案し、また、日常の行政も司りました。
官僚の選出も10部族制にのっとり、10人同僚制が広く採用されるようになりました。
中でももっとも重要なのは、将軍職ストラテーゴスの創設です。10人の将軍は、それぞれの部族の戦士たちを統率する役として選ばれたのでした。
従来、ポリスを代表する最高の役職は、アルコーンであって、筆頭のアルコーン・エポーニュモス、祭祀のバシレウス、軍事のポレマルコス、それに、司法の6人テスモテタイの、合わせて9人でした。アルコーンの任期は1年でしたが、前5世紀に入って、ほとんどの役職と同じく、籤引きになりました。しかし、将軍職は、毎年民会で選ばれ、しかも、任期に制限がなかったので、最盛期のアテーナイでは、アルコーンに代わって、最も重要な役職になりました。実際、ペルシア戦争の時代にも、テミストクレース(前528年頃~前462年頃)は将軍職についていますが、とりわけ、アテーナイの最盛期には、ペリクレース(前495年頃~前429年)が、将軍として、14年間も、アテーナイの政治を指導したのでした。
〔2〕アテーナイ近郊、アッティカを散策
ペルシア戦争の古戦場、マラトーン さて、アテーナイの東の門、ディオカレース門を出た道は、リュケイオンの体育場を過ぎて、東北へ約40キロメートル、マラトーンへ通じていました。
マラトーンはペルシア戦争の古戦場です。前490年、ミルティアデースの率いる9千のアテーナイ軍は、友邦プラタイアイ軍1千とともに、上陸した2万のペルシア軍を打ち破りました。これは、アテーナイの民主制と重装歩兵市民の勝利でもありました。
マラトーンの勝利を報せるため、アテーナイ兵の一人が、戦場からアテーナイまで力走して、「喜べ、勝てり」と叫んだまま息絶えた、という話が伝えられています。この故事にちなんで、マラトーン‐アテーナイ間の距離、おおよそ40キロメートルの競走が、第1回近代オリンピック(1896年)(図27参照)から、競技種目に加えられたのでした。
マラトーンには、アテーナイ軍、プラタイアイ軍、それぞれの戦死者の塚(図25)があって、歴史に残る戦いの様子が偲ばれます。近くには博物館も建てられています。
ところで、マラトーン(現マラトン)は、現代アテネの人々にとっては、大切な水源地です。マラトン湖が拡張され、ここから水道が引かれているのです。
それに、古代に戦いのあった海岸近くは湿地帯でしたし、一般に乾燥しているアッティカ(アッティケー)地方としては、マラトーンは水に恵まれているところのようです。
水といえば、私には、マラトーンに忘れられない思い出があります。二度目に訪れたときのことでした。それは激しい雷雨に見舞われ、ギリシアの主神ゼウスの武器が
キタイローンの山麓、プラタイアイ なお、プラタイアイは、オイディプースの悲劇ゆかりの、キタイローン山の北麓、ボイオーティアー地方の南の端にあって、アッティカ地方はすぐ隣です。テーバイから南へ約15キロメートル、あるいは、エレウシースから西北約30キロメートル、道の両側に、プラタイアイの市壁(図26)の遺構が見られます。
第1回近代オリンピック さて、第1回近代オリンピックのマラソン・コース(図27)は、マラトーンから海岸沿いに南へ走り、ペンテリコン山(現ペンデリ)の南麓を西へ、ヒューメーットス山(現イミトス)の北をかすめて、アテネの競技場スタディオン(図28)へ向かっていました。
競技場といえば、1896年、第1回近代オリンピックの終幕を飾る場面が思い起こされます。7万人を超える観客が待ちかまえている競技場へ、真っ先に駈け込んで来たのは、予想もされなかったギリシアの走者、羊飼いの身なりをしたスピディリオン・ルイスでした。彼は科学的な練習などはまったく知らず、断食と祈りで試合の準備をしたのでした。彼が二人の王子に伴われて国王の前へ進み出たとき――当時のギリシアは、ヨーロッパ列強から王制を押し付けられていました――、あたかも古代ヘラスがよみがえってきたかのように――ギリシア人は、彼らの勢力範囲をヘラスと呼んでいました――、万雷の拍手が起こりました。古代オリュンピアの伝統に輝く開催国ギリシアが、この最後の競技まで、優勝者を出してはいなかったのです。この劇的な情景は、近代オリンピックの創始者ピエール・ド・クベルタンの回想録にも、臨場感あふれる筆致で描かれています。
生き生きとした虚構 ところで、マラソン競走の根拠になったアテーナイ兵の力走は、歴史的な事実ではなかったようなのです。ペルシア戦争について詳しく記しているヘーロドトス(前485年頃~前425年頃)の『歴史』には、まったく触れられていませんし、この話をはじめて記しているのは、戦後150年ほど経ってから書かれたものなのです。おそらく、合戦後、全軍がアテーナイへ急いで引き返したことや、合戦の直前、援軍を頼む使者がスパルタへ非常な速さで走ったことなどから、いつのまにか創作された話だったのでしょう。
また、先にも述べましたように、プラトーンは、アカデーメイアにあった公共の施設を使って学校を開いたのでした。したがって、あの有名な言葉、「幾何学を知らざる者は入るべからず」も、それが学校に掲げられていたとは思われません。
つまり、人間というものは、たんなる真実よりも、生き生きとした虚構に惹かれるものなのでしょう。
時計回りの文化、反時計回りの文化 さて、話は変わりますが、第1回近代オリンピックのトラック競技には、現在と非常に違ったところがありました。一周は400メートルでしたが、古代の競技場と同じく、直線コースが長くて、曲線コースは急な、いわゆるヘアーピン・カーヴになっていましたし、それに、反時計回りではなく、時計周りに走ったのでした。この時計回りの徒競走は、10年後にふたたびアテネで開かれた中間大会まで続きました。
それでは、古代のギリシアには、時計回りの伝統や習慣があったのでしょうか。そうなのです、古代のギリシアには、時計回りの伝統や習慣があったと思われます。
例えば、身近なものでは、貨幣の刻字は、とりわけ、前5世紀半ば以降は、時計回りに付けられていますし、幾何学図形に付けられた記号も、時計回りになっています。文様でも、例えば、三脚
それに対して、古代ローマには、反時計回りの伝統や習慣があったと思われます。アウグストゥス帝はローマ市を14の区に分けましたが、その順序などは反時計回りのよい例でしょう。
ちなみに、佛教は、須弥壇の周りを時計回りしますし、四国八十八ヶ所の遍路道も時計回りですが、キリスト教は、祭壇の周りは反時計回りするのです。
そして、私たちの日本の文化も時計回りの文化です。その典型的な例として、佐渡に残る車田植えを挙げることができましょう。三人の早乙女が、田の神の依代(よりしろ)となる苗の束を中央に植え、その周りを時計回りに後ずさりしながら、苗を植えて行くのです。
時計回りは、太陽の動きを象徴していると考えてよいでしょう。他方、反時計回りは、北極星の周りを巡る星々の動きを象徴していると考えられます。時計回りの文化は、農耕社会に根差し、反時計回りの文化は、遊牧社会に根差しているのです。
この時計回りの文化、反時計回りの文化は、非常に興味深いテーマですが、先に筆者は、やはりこのSPAZIO誌63号、64号で、詳しく論じておりますので、興味をお持ちの方はこれらの論考を御高覧下されば幸いです。
ペンテリコンの石切場 ところで、アテーナイとマラトーンとの間、アテーナイの東北を限る山並みが、先にも述べたペンテリコン(1,110メートル)です(図30)。あのパルテノーンも、アゴラーのヘーパイストスの神殿も、このペンテリコンのきわめて上質の大理石で造られていて、石切場が開発されたのもその時代、前5世紀でした。初めて大理石を切り出したのは、後に義賊の名前を付けられた、ダヴェリスの洞窟の辺りなのですが、今は山腹の広い範囲で採石されているので、そこを探し当てるのは容易ではありません。
最近の考古学の成果 ペンテリコンの南麓にあるガルゲーットスは、エピクーロス学派の人々が、前4世紀の末から前3世紀の初めの頃にかけて、創始者エピクーロスを中心として、共同生活を営んでいたところとして知られています。エピクーロスはサモスで育ちましたが、生まれたのはやはりここガルゲーットスだったと思われます。
このエピクーロスの学校の跡はまだ発掘されていないようですが、1995年に訪れたときには、神殿の基礎部分と思われる遺構(図31)が発掘されたところで、携わって居られる二人の女流考古学者からお話しを伺えたのはまことに幸いでした。すでに10年以上経ちましたので、彼女たちの研究の成果をここでお話ししても差し支えはありますまい。
これより先、アテーナイのアゴラーでは、ゼウスのストアーの東南、パンアテーナイア祭の道との間に、砕石に覆われた神殿の基礎部分があって、それは、パウサニアースに記されている、戦さの神アレースの神殿の遺構に違いないとされていました。ところが、覆っていた破片からは、この神殿は前5世紀の第3・4半期に建てられたと考えられるのに、基礎部分の方は、前1世紀に造られたとしか考えられず、どうやらこの神殿は、前1世紀に、アゴラーへ移築されたに違いないと結論されていたのでした。
そして、ガルゲーットスで発掘された神殿の基礎部分と、アゴラーのアレースの神殿の基礎部分とは、それらの寸法が一致したと聞いています。もしそうであれば、アゴラーのアレースの神殿は、前5世紀に、ガルゲーットスに建てられたものを、前1世紀に、移築したものであったことになりす。アレースは、ギリシア人の間ではあまり信仰の対象にはなりませんでしたが、戦さの神だからでしょうか、ローマ人には人気があったようで、おそらくこの神殿も、あのガイウス・カエサルの同姓同名の孫が、「新生のアレース」と称えられていたので、彼のために、アウグストゥスによって移築されたものでしょう。
それにしても、元のガルゲーットスの神殿に祀られていたのは、どのような神だったのでしょうか。なんとなくアレースではなかったような気がするのですけれど。エピクーロス学派にしても、彼らの求める人生の快楽は、心の平静にあったのですから。
泉と神々 さて、次に、アテーナイの東を限るヒューメーットス(現代ギリシア語では、イミトス、1,027メートル)の山並みは、水に恵まれ、イーリッソス河の水源地でもありました。泉も多く、泉の近くには、それぞれ、神々を祀る社があり、アテーナイの飲料水も、以前は、この山の泉から引かれていたのでした。――泉は残っていても、今そこに見られるのは、昔の石材を使った、キリスト教の聖堂や修道院の建物なのです――。
ヒューメーットスの大理石は、その石の質がペンテリコンに比べて劣るとはいえ、採石があまり進められなかったのは、この山がさまざまな神々の祀られた聖なる山であったからでしょう。
イーピゲネイアの悲劇 さらに、ヒューメーットスの山並みを東へ越えれば、海岸に近いブラウローンには、女神アルテミスの神域が遺されています(図33)。アテーナイからは25キロメートルくらいでしょうか。
ここブラウローンは、エウリーピデース(前485年頃~前406年頃)の悲劇『タウリスのイーピゲネイア』ゆかりの地です。話の順序として、ホメーロスの叙事詩『イーリアス』に記され、やはりエウリーピデースの悲劇『アウリスのイーピゲネイア』の舞台になった、アウリスへ、先に訪れることにしましょう。アウリスは、アッティカ地方を少し出て、ボイオーティアー地方へ入りますが、北の海岸にあって、エウボイア島と向かい合い、カルキスからは遠くないところにあります。
トロイアー遠征のギリシア軍の船団は、ここアウリスに集結しましたが、アルテミス女神の怒りを買って順風が得られず、全軍を率いるミュケーナイの王アガメンノーンの娘、イーピゲネイアが犠牲に供せられることになります。アキレウスとの縁談を口実に呼び寄せられたイーピゲネイアは、事情を知り、父に哀願しますが、やがてギリシア軍のためにこの身を捧げようと決心するのです。祭壇へ進むイーピゲネイアの姿は消え、身代わりの鹿が横たわっていました。
このアウリスのアルテミスの神殿の遺跡は、周りは丘に囲まれているのに、低湿地にあって、見付け難いところです(図32)。
さて、やはりエウリーピデースの『タウリスのイーピゲネイア』によれば、アルテミス女神はけなげな乙女の命は奪わず、黒海の北岸タウリスへ連れ去り、イーピゲネイアはこの地で女神に仕えることになります。アルテミスの巫女は異邦人を女神に捧げなければなりませんでした。そこへ弟のオレステースが、アポローンの命により、女神像をアッティカへ持ち帰ろうと、この地へやって来ます(図34)。捕らえられ、曳き立てられてきた若者が弟であることを知ったイーピゲネイアは、アテーナー女神の助けも得て、二人手をたずさえて、アルテミス女神像をブラウローンへ捧持することができたのでした。
ブラウローンには、神域の近くに博物館もあって、『神々の浮彫』(図35)と名付けられた、アルテミス女神一家の群像、向かって右から、アルテミス、兄弟神のアポローン、母神レートー、父神ゼウス(前5世紀末、あるいは、前4世紀初め)、「熊」(図36)と呼ばれていた幼い巫女たちが、野兎や小鳥を抱いている、愛らしい彫像(前4世紀)などを観ることができます。
ところで、このブラウローンのアルテミスの神域も、やはり丘の側の低湿地にあるのです(図32参照)。
女神の、地母神の神殿は低湿地に建てられた
考えてみますと、アウリスやブラウローンのアルテミスの神殿ばかりではなく、エペソスにある、二重周柱様式のアルテミスの大神殿(前560年~前550年)も、低湿地に建てられていました。さらに、サモスにある、二重周柱様式のヘーラーの大神殿(前570年~前560年)も、やはり、流れの速いインブラソスの河口に近く、低湿地に建てられていたのです。そして、ロイコスとともにサモスのヘーラーの神殿の建築にたずさわったテオドーロスは、低湿地の経験者として、エペソスへ招かれ、アルテミスの神殿の建築にも加わったのでした。
外にも、リューディアーの首都サルディースのアルテミスの神殿は、砂金で知られるパクトーロス河畔に建てられていました。また、スパルタのアルテミスの神域も、エウロータス河畔にあって、いわゆるスパルタ教育はここで行なわれたのでした。。
そして、ポセイドーニアー(羅パエストゥム)の北、シラロス(伊セーレ)河口に近く、アルゴー船のイアーソーンが捧げたといわれる、ヘーラーの古い神域があります。また、コリントス湾の岬、ぺラーコーラーのヘーラーの神殿は、前8世紀の初めに建てられたものですが、波打ち際にあるといってもよいでしょう。
さらに、ボイオーティアーのアテーナイは、アッティカのアテーナイよりも古い都市でしたが、これも低地にあったため、アテーナーの神殿もろとも、コーパイーダ湖に沈んだのではないでしょうか。ミーレートスのアテーナーの神殿(前5世紀前半)も、また、低地に建てられていました。
それにしても、低湿地は、基礎を固めるのが難しく、木造ならともかく、石造りの大きな建物に適した土地とはとうてい考えられません。エペソスのアルテミスの大神殿にしても、約200年の後、前356年に火災に遭い、前334年~前325年に再建された新しい神殿は、もとの神殿と同じ設計で建てられたのでしたが、低湿地のために沈んだからでしょう、基壇だけは高くしたのでした。
それにもかかわらず、女神の神殿が多く低湿地に建てられているのは、どうやら、女神の神殿は、もともと低湿地に建てるしきたりがあったからではないでしょうか。
主な女神たちは、地母神であり、死を司る地下神、死と再生、豊饒と多産の女神でした。母なる大地と呼ばれるように、大地は生命の産み出されるところです。とりわけ低湿地は、動植物の生まれ出るところであり、冥界にも近いところと信じられていたのでしょう。時代は、やがて、母系制から、父系制へと代わり、男神の神殿が高所に、丘の上に建てられるようになって、女神の神殿もしだいにそれにならうようになって行ったのではないでしょうか。
それに、低湿地は女性の秘所との類推、そして、神殿の位置の高低は男女の交わりの体位との類推も重なっているのでしょう。外にも、例えば、母神デーメーテールと姫神ペルセポネーとを祀るエレウシースには、その神話にも現われるように、井戸や洞窟があって、それらはいずれも女性を象徴するものではないでしょうか。
夢占いのオーローボス なお、アウリスへ行ったついでに、オーローポスへも立ち寄ってみましょう。ここには夢占いで有名なアンピアラーオスの神殿がありました。
アンピアラーオスはアルゴスの人で、思慮深く、武勇に秀でた、偉大な予言者として知られていました。しかし、心ならずも、「七人の将軍」の一人として、テーバイ攻めに加わりましたが、敗走している時、ゼウスの計らいで、大地が裂けて、戦車もろとも、冥界へ呑み込まれてしまったのだそうです。その場所がここオーローポスだといわれています。
ラウリオンの銀山 さて、ブラウローンへ戻って、海岸沿いに南へ約25キロメートル、ラウリオンの銀山があります。この銀の鉱山はアテーナイの重要な財源でした(図37)。
前483年、大きな鉱脈が見付かって、国庫が大いに潤ったとき、時の指導者テミストクレースは、慣習にさからい、余剰金を市民に分配せず、100隻にも上る艦船を建造しました。それは、ペルシアの、マラトーン上陸に次ぐ、再度の来寇に備えてのことといわれています。そして、テミストクレースの見通しは誤りなく、前480年、アルテミシオン沖の海戦、次いで、サラミースの海戦において、ギリシア軍はペルシア軍に決定的な勝利を収めることができたのでした。
このラウリオンの銀山は、つい最近まで操業を続けていました。裏の山手には、多くの廃坑が口を開けているのが見られます。
スーニオン岬の夕照 ラウリオンからさらに南へ約500メートル、スーニオン岬へ着きます。岬の先端近くには、海の神ポセイドーンの神殿が聳えています。基礎はポロス石で、前490年より少し前に造られたようですが、上の建物は、アゴラーのヘーパイストスの神殿と同じ建築家によって、ペルシア戦争後、前444年頃に建てられたと考えられています。
昔、遠い船旅から帰ってきた人々は、岬に聳えるこの神殿を仰いで、故郷へ帰ってきた想いを噛み締めたことでしょう。
それに、この神域で迎える夕照の美しさはまた格別です(図38)。外の遺跡とは違って、ここが遅くまで開かれているのは嬉しいことです。
なお、スーニオンには、前450年頃建てられた、アテーナーの神殿もありました。この神殿は、ローマの建築家ウィトルーウィウス(前1世紀)の著『建築書』にも記されています。
港町ペイライエウス、古代の軍港と市壁 スーニオン岬から、今度はサローニコス湾岸に沿って、西北へ50キロメートル近く、二つの港町パレーロンとペイライエウス(現ピレエフス)があります。
パレーロンは神話にも出てくる古い港ですが、浅くて、吹きさらしなので、海軍を増強したテミストクレースは、前5世紀初め、その西隣のペイライエウスに軍港を整備し、この街を囲むだけではなく、アテーナイまで結ぶ長い市壁を築きました。
さらに、ペリクレースの下で、前445年、ペイライエウスは、ヒッポダモスの都市計画にしたがって、碁盤目の街路を持つ都市として造成されました。そして、商業港としても、アテーナイ、アッティカ地方を後背地として、めざましい発展をみせました。
円形に造成された、古代の二つの軍港(図39)も、テミストクレースによって、また、前5世紀末、コノーンによって築かれた市壁も、部分的には、今でも見ることができます。しかし、ヒッポダモス方式の街路については、今後の発掘を待たなければならないでしょう。あるいは、都市全体としてではなくて、いくつかの部分に分け、それぞれが碁盤目の街路に造られていたのかもしれません。
考古学博物館も古代の軍港ゼアの近くにあります。女神キュベレーの坐像(前4世紀)(図40)が、出所の同じライオン像を従えて、この博物館を代表するものといえましょう。女神像の側に並べられている、浮彫『患者を治療するアスクレーピオス』(図41)は、アッティカ地方への入口ペイライエウスにおける、アスクレーピオス信仰の普及を物語っています。また、ピレエフスのクーロス(青年像、前525年頃)は、アポローン神像と思われ、貴重なアルカイック期のブロンズ像(図42)です。外にもブロンズ像としては、アテーナー神像(前325年頃)、それに、2体のアルテミス神像が収められています。
博物館と軍港ゼアとの間には、劇場が遺されています。前2世紀からローマ時代にかけてのものです。
食事には、ゼアの周りに並ぶタヴェルナで、魚料理を注文しましょう。実物の魚を見せられて、どれを食べるのか決めるのも珍しい経験になることでしょう。
エーゲ海の島々への定期船も、観光船も、もちろんピレエフスの港から出航しています。
サラミースの海戦を偲んで 近くの島アイギーナ(エギナ)へ行ってみましょう。港を出るとすぐ、右舷に見える島は、サラミース島です。あのサラミースの海戦(前480年)は、この島の東北側、本土との間の狭い海峡、サラミース水道で行なわれたのでした。
サラミースの海戦は、ギリシア連合軍のペルシア軍への勝利を決定付けたものでした。そして、これは、自由な市民による民主制の権力者による専制制への勝利でもありました。
このサラミース水道は、エレウシースの海岸からも真南に見えます。
アイギーナ島 さて、アイギーナは、かつてはアテーナイに先立つ豊かな都市国家でした。島の東端に聳える女神アパイアーの神殿(図43)も、前6世紀末か、前5世紀初めに建てられました。神殿の柱は、それぞれ一本の石材から彫り出されたもので、後の時代のように、いくつかの石を積み上げたものではありません。神殿に飾られていた彫刻(図44)は、アルカイック期を代表するもので、今はドイツ、ミュンヘンの彫刻館に展示されています。
島の西端エギナの港までは、ピレエフスから1時間と少々。そこから神殿までは約12キロメートル、バスで30分そこそこです。島のお土産はピスタチオ‐ナッツでしょうか。
そして、アテネへ帰るには、ピレエフスから地下鉄に乗るのが便利でしょう。
どうやら私たちは、アテーナイ近郊を巡るのにも、時計回りをしたようですね!
SPAZIO誌上での既発表エッセー 目次
- 『受胎告知』の図像における処女マリアと大天使ガブリエルとの配置について
no.56(1997年12月発行) - 聖なる数10をめぐる随想 ─ 女神ヘーラー信仰とピュータゴラース
no.58(1999年4月発行) - 哲学のふるさとミーレートス-その都市計画に秘められたもの
no.59(2000年4月発行) - -知の楽しみ、創造の悦び- 逸話で巡る地の世界 no.60(2001年4月発行)
- 時計回りの文化、反時計回りの文化(1) no.63(2004年8月発行)
- 時計回りの文化、反時計回りの文化(2) no.64(2005年7月発行)