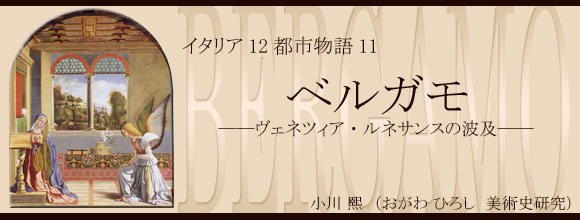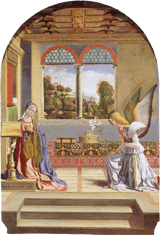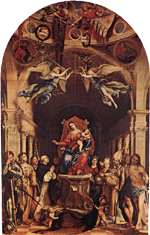〔1〕ランゴバルド王国の誕生
ロンバルディーア州の都市としては、これまでマントヴァを取り上げただけだった。しかし自然地理的にはマントヴァはロンバルディーアの東南の端にあり、むしろ広大なポー河流域地帯に含まれ、政治史的にも文化史的にも、より南のエミーリア=ロマーニャやトスカーナとの関係が深かったといえる。ロンバルディーアの州都はミラーノであり、これはいうまでもなくイタリア第二の大都市で、ローマを凌ぐ経済の中心地であるが、それゆえにこの連載の対象外とするので、他に重要な都市といえばまずパヴィーア Pavia がある。そもそもロンバルディーアとは中世初期に北から侵入して定着したランゴバルド人に由来することは前にも触れたが、その王国の首都的な都市がパヴィーアであり、イタリア史には頻繁に出てくる地名である。しかし中世以降は特に文化史的にほとんど役割を果たすことがないので、ここでは割愛するしかない。そこで私が選んだのはベルガモである。その少し東にあるブレーシャ Brescia もまた、ベルガモと似通う部分が多分にあって捨て難いのだが、ベルガモはミラーノからわずか30キロの地点にあってロンバルディーア的な要素が強いことと、後に詳述するように、15世紀以降、ヴェネツィアとミラーノの勢力が衝突する接点をなしていることがきわめて興味深いからである。なおベルガモはこの連載で取り上げた中で最北に位置することになる。
ランゴバルド人到来以前の古代について簡単に要約しておくと、紀元前1200年頃最初にこの地に住み着いたのはリーグリ人 liguri だったと思われる。リーグリというのは、現在のジェーノヴァを中心とするリグーリア州に名を残すように、イタリア半島の西北部から南フランスにかけて定住していた原始民族で、素朴な半農半牧を業としていたと思われるが、文献資料も建築的遺構もほとんどない。さらには半島中部のウンブリ人もベルガモあたりまで到達していたと考えられているが、これも全く痕跡がない。リーグリ人もやがて北からはケルト人、南からはエトルリア人の圧力を受けて、次第にアイデンティティを失って いった。エトルリア人はベルガモにまで到達して拠点を築いたという説もあるが痕跡はなにもない。むしろ前6世紀の半ば頃、ケルト人が都市を造ったことはほぼ間違いなく、ケルト語で「山」を意味するBergと「家」を意味するHemが合体して、Berghemと名付けられたといわれている。いまでも地元ではベルゲムということもあるらしい。そしてローマ人によって完全に征服されたのは前196年のことであり、Bergomumと呼ばれ、帝政期には第11管区に所属することになる。
以後のゲルマン民族の侵入については、前号『パルマ』で述べたように、北イタリア諸都市がほぼ同様の経過を辿るといってよい。すなわち、まずアラリクスの率いる西ゴートに攻略され、ついでアッティラのフン族、ガイセリックのヴァンダル、そしてオドアケルの一族、東ゴートのテオドリクスと続き、ビザンティンとのゴシック戦争を経て569年にランゴバルド人がベルガモを獲得することになる。ランゴバルド人は774年まで二百余年の間、北イタリアの広い領域にわたる王国を築き、この時代にラテン文化と接触して文明化され、最終的にはカトリック化される。経済も依然農業中心であったが繁栄し、ベルガモで金・銀貨の鋳造が行われたといわれる。この間の史実は「空白期」のように一般にはあまり知られないが、幸運なことに、8世紀のランゴバルドの宮廷書記、パウルス・ディアコヌス Paulus Diaconus がラテン語で書き残した『ランゴバルド史』(Historia Langobardorum、邦訳なし)によってかなり正確に再現することができる。
ランゴバルド王国滅亡の後、ベルガモはほぼ三世紀にわたってカロリング王朝の支配を受け、司教伯による統治が行われた。そして12・13世紀にはここでもやはりコムーネの時代を迎えて共和政的な体制が持続し、繊維産業を主とする経済も発達した。しかし、他の都市でも見た通り、やがて教皇派と皇帝派の対立が生じ、前者を代表するスアルディ家 Suardi と後者を代表するコッレオーニ家 Colleoni という有力者同士の抗争が深刻化する。1295年にスアルディはミラーノのヴィスコンティ家に支援を求め、コッレオーニを追放することに成功する。しかしそのことによってベルガモは実質的にヴィスコンティ家の手中に入る結果となり、その支配は15世紀の初めまで七十年ほど続いた。その政治は市民に対する圧制というにふさわしいものだったらしいが、後述するような現存するキリスト教のいくつかのモニュメントが建造された。そして1428年、ヴェネツィア共和国に編入され、それがベルガモの文化史に大きな影響を与えることになるのだが、詳細は後回しにして、ベルガモ統治の歴史はここで一旦打ち切っておくことにしよう。
〔2〕中世のベルガモ:「高い都市」
アルプスの斜面を降り切った地点の平野にある現在のベルガモは、人口12万弱を擁する中都市であるが、ミラーノとヴェネツィアを結ぶ鉄道の駅を降り立って北側を見ると、高さ100メートルほどの小高い丘が目に入る(図1)。古代から中世初期までの人々が住み着いたのはすべてこの丘の上だった。ケルト人が「山」を意味する地名を与えたのはそのゆえであった。南側の麓から平地一帯に居住区が広がったのは15世紀頃からであり、現在は「高い都市」(Città Alta)と「低い都市」(Città Bassa)と区別して呼ばれている。近代都市ベルガモの市政の中心は「低い都市」であり、「高い都市」は中世の建築や街路がほとんどそのままに保存された歴史地区であって、ベルガモは完全に区別された二つの異質な要素から成り立っているのである。下から上に登るためには、曲折した道路のほか、山麓から一本のケーブル・カーが通じており(1887年敷設)、わずか数分を要するのみである。ラツィオ州やトスカーナ州の多くの都市では「歴史的中心地区」(centro storico)の保存と開発の矛盾が共通の課題なのだが、その点ではベルガモは幸運だったといえるだろう。
「高い都市」はすでにローマ時代から城壁で囲まれていたが、その後13世紀に一度改修され、さらにヴェネツィアの統治下に入るとすぐに、より強固な壁(Muraine)が造られた。しかしヴェネツィアは1561年から「山」をそっくり要塞化しようと試み、中世の壁を壊してより外側に頑強な城壁を築き、それが現在残っているものである。ただし皮肉なことに、というか幸いなことにというべきか、ベルガモはその後一度も外敵の攻撃を受けることがなかった。なおこの拡張工事に当って、500戸以上の市民の住居のほか、伝説によれば4世紀初頭にこの町で殉教し、ベルガモの守護聖人となった聖アレクサンドロス(アレッサンドロ)に捧げたおそらく5世紀頃の聖堂も撤去された。これはきわめてローカルな聖人であり、征服者はこの土地の信仰を無視したのであった。
城壁には東西南北に四つの門がある。ケーブル・カーはその城壁をトンネルで突き抜けていきなり町の中心部に出るようになっているが、車や徒歩で登るには東側のサンタゴスティーノ門がメインの入口になっている。北側のサン・ロレンツォ門を除く三つの城門の最上部に、ヴェネツィアの象徴である有翼のライオンの紋章が浮彫で表されており、栄光の記憶をとどめている。城壁内は東西方向の最長部でも1500メートル足らずの距離だから、徒歩の散歩にふさわしい空間を構成している。ここでは古い煉瓦造りの建物に挟まれた狭い道が入り組み、ここだけ歩いていると、ふとウンブリアやトスカーナの小さな中世の町を思い出す。中心部に近い辺りには、メルカート・デル・フィエーノ(干し草市場)、ケーブル・カーの終点となっているメルカート・デッレ・スカルペ(靴市場)、メルカート・デル・リーノ(麻織物市場)、メルカート・デル・ペーシェ(魚市場)といった名前のついたいくつかの小さな広場があり、中世都市の庶民的な活況が蘇ってくる。
ガイド・ブックお勧めの街路の一つがドニゼッティ通りである。ベルガモが誇りとする19世紀のこの作曲家の生家がここにあるほか、15・16世紀の上流階級の邸宅が立ち並んでいる。しかしより興味深いのはそのうちの一軒が中世の造幣所だったことだ。12世紀頃からヨーロッパの特に北イタリア諸都市では急速に商業が活発となり、ヴェネツィア、ジェーノヴァ、フィレンツェなどで各種の貨幣が鋳造されたことはよく知られているが、ベルガモでもペルガミヌス pergaminus という特有の貨幣が造られていた。それはすでにランゴバルドの時代に遡るのではないかとも考えられているが、少なくとも1238年の確かな記録があるということだから、フィレンツェのフィオリーノ fiorino(1252年)やヴェネツィアのドゥカート ducato(1284年)よりも早いわけだ。それというのもベルガモの北側のアルプス山麓の峡谷地帯にまさに金鉱や銀鉱が存在するという地理的な条件が有利だったのかもしれない。ペルガミヌスの鋳造所は有力者の一人、リヴォーラ家が管理していたが、政争に敗れた後、コッレオーニ家に移管された。ともかく、1254年にはベルガモの支庁舎に各地の自治都市の代表者が集合して、通貨システムについて話し合い、金銀の重量の基準としてベルガモのものが採用されたという(Beatrice Gelmi-Valeriano Sacchiero『Bergamo,passo passo』)。しかし16世紀頃にフィオリーノやドゥカートがヨーロッパの主要な通貨としての地位を得るにしたがい、ペルガミヌスは消滅していったと思われる。
「高い都市」の中心部にはヴェッキア広場 Piazza Vecchia とドゥオーモ広場 Piazza Duomo という二つの広場があり、そこに面して中世の聖と俗の権力を代表する建物が集中し、閑雅なたたずまいを見せている。ある年の九月、ヴェッキア広場の片隅にはしゃれた感じのオープン・カフェが出ており、人慣れた鳩がパン屑を求めてテーブルの上まで舞い降りようとしていた。隣ではいかにも上流家庭の主婦といった中年女性が三人ほど茶を飲みながら、つい先頃までのヴァカンスの旅先の出来事に話を弾ませていて、ヨーロッパのよき時代の名残りを垣間見た気がした。広場の北側にはかつて9世紀に建てられたサン・ミケーレ・アッラルコ S.Michele all'Arco というベルガモの最も古い聖堂の一つが存在したが、その後17世紀から19世紀まで市庁舎として使われたパラッツォ・ヌオーヴォの一部として取り込まれ、教会堂としての機能は失われてしまった。現在は建物全体が市立図書館となっていて、イタリアでも有数の蔵書を誇っている。
ついでながら「高い都市」の東端に近い所にサン・ミケーレ・アル・ポッツォ・ビアンコ S.Michele al Pozzo Bianco という小さな聖堂があり、これは8世紀には記録に登場する古いものだが、サン・ミケーレすなわち大天使聖ミカエルに捧げた聖堂が二つもあることは偶然ではない。キリスト教化されたランゴバルド人が最初にみずからの守護聖人として崇めたのが聖ミカエルである。つまり悪竜を退治したゲルマンの伝説的英雄ジークフリートに聖ミカエルの姿を重ね合わせたのである。後者の聖堂内部には15世紀に描かれた<悪竜を退治する聖ミカエル>のフレスコ壁画も残っている。そういえばイタリアには聖ミカエルの名を冠する教会は多くないことに気づく。なるほどランゴバルド王国の首府だったパヴィーアには非常に美しいロマネスクのサン・ミケーレ聖堂があり、プーリア州のモンテ・サンタンジェロには聖ミカエルに捧げた有名なサンクチュアリがあって中世以来の重要な巡礼地となっているが、これもランゴバルド人がナポリに近いベネヴェントに築いた公国によって6世紀に開かれたものである。そしてもちろん、イタリア外ではノルマンディーのモン・サン・ミシェルを忘れるわけにいかない。思うに、ランゴバルド人の聖ミカエル崇敬は、ローマ人とちがって、初期キリスト教時代の迫害を経験しなかったためにかれらの先人に殉教者がいなかったことと無縁ではないだろう。しかし同時に、ランゴバルド人の攻撃的・戦闘的な性向が悪を力で滅ぼすヒーローを好んだのではあるまいか。
一方、ヴェッキア広場の西側に面して立つのはパラッツォ・デル・ポデスタであり、1340年に前述のスアルディ家の邸宅として建てられたが、1428年以降、ヴェネツィアのポデスタpodestà(司法長官)の公邸となった。現在は外国語大学の校舎として使われている。
〔3〕傭兵隊長コッレオーニ
ヴェッキア広場の南側を塞いでいるのは、中世自治都市の市政の中心であったパラッツォ・デッラ・ラジョーネである。12世紀に建てられた当初の形はほとんど失われ、現在の姿は1520年頃のものである。ゴシック様式とルネサンス様式が混在し、あまり美しい建築とはいえない。左奥の方に高い塔が見える。これは12世紀に教皇派のスアルディ家が戦闘のために建てたものだが、その後コムーネの鐘塔となり、さらに15世紀初めに現在見られる時計が取り付けられた。市民に時を知らせたり種々の合図を送る鐘塔は、シエーナでも見たように、中世自治都市の象徴として一般的なものではあるが、17世紀に新たに取り換えられた大鐘(Campanone)と地元で呼ばれるベルガモの鐘は、その鳴らし方がおもしろい。すなわち中世以来の伝統として消灯(あるいは市壁の閉門)を告げる鐘が夜10時に打たれるのだが、いまでもそれがなんと180回続くのだそうだ。その度数の由来についてはよくわからない。
パラッツォ・デッラ・ラジョーネの一階の東側は吹き抜けの通路になっていて、ドゥオーモ広場に通じている。この場所こそローマ時代にフォールムのあったところと考えられ、中世には市庁舎とドゥオーモに面し、市民の政治的・宗教的な集会が行われた。広場の東側にあるドゥオーモは1100年頃には完成していたが、その後15世紀のミラーノの建築家フィラレーテが関わったのを始め、改修が繰り返されて正面ファサードは19世紀後半にできたもので、あまり重要ではない。それよりも、南側に並ぶサンタ・マリーア・マッジョーレ聖堂(図2)と、それに接続するコッレオーニ礼拝堂(Cappella Colleoni)は、ベルガモの中世を代表する建築遺産である。サンタ・マリーア・マッジョーレは1137年に着工されたロマネスク様式の聖堂である。この聖堂にはファサードがないのが変っていて、左右の翼廊の端にプローティロ protiro という小玄関があって、それが入口になっている。この部分には建築的・彫刻的なさまざまの細工が取り付けられ、それが一つの見所になっているが、その作者はジョヴァンニ・ダ・カンピオーネ Giovanni da Campione である。カンピオーネ一族については『モーデナ』の項で紹介したように、コーモ地方出身の石工の集団であり、12世紀末から14世紀にかけて主にポー河流域地方で活躍した。ベルガモで働いたジョヴァンニはその最後の世代に属し、ロマネスクからゴシックへの移行期に位置付けられる。ドゥオーモ広場に面した北側のプローティロでは扉口の上に二重の柱廊(loggia)を設け、六体の彫刻を置いた(1353年)。そのうち下段中央の騎馬像は聖アレクサンドロスであり、大天使ミカエルを信奉したランゴバルド人到来以前のベルガモの守護聖人がこうして再登場するのはおもしろい。一方南側のプローティロは全く趣を変え、扉口の上に突き出たアーチ構造の穹窿の部分を支える柱の下には二頭のライオンと二体のテラモンが置かれている。最上部には横一列にキリストと十二使徒の浮彫が施され、その上にスレート葺きの屋根がかかる。
コッレオーニ礼拝堂内部の壁画(14世紀中頃、作者不詳)。上段中央の<最後の晩餐>においては、イエスは一人おいて右隣のユダにパンを与えているのが特徴的で、聖体を否定する異端に対するカトリック教会の姿勢が強調されていると思われる。なおユダだけが頭上に光冠を頂かずに特化されている。
ドゥオーモ広場に面してサンタ・マリーア・マッジョーレ聖堂の右に接続するコッレオーニ礼拝堂(図3)は、1437年に再びヴィスコンティ家がベルガモに攻め入った時、ヴェネツィア共和国の傭兵隊長としてこれを撃退したバルトロメーオ・コッレオーニの霊廟として1476年に造られたものだ。バルトロメーオはその後フランチェスコ・スフォルツァの側についた時期もあったが、最終的にはヴェネツィアのために17年間にわたって各地に転戦した。パードヴァのガッタメラータと並んで15世紀の傭兵隊長として最も代表的な存在であり、フィレンツェの彫刻家アンドレーア・ヴェロッキョが原型を制作した青銅の騎馬像が現在ヴェネツィアのサンティ・ジョヴァンニ・エ・パオロ広場に置かれている。遺言により、サン・マルコ広場に置かれることを望んだが、それはならなかったようだ。
彼は傭兵隊長の身分に甘んじ、一国の領主となる野心をもたなかったようだが、地元ベルガモでも灌漑工事に力を入れたり、芸術を保護するなどして一際人望が厚かったらしい。霊廟の設計者はロンバルディーア諸都市で活躍したジョヴァンニ・アントーニオ・アマデーオ Amadeo である。フィラレーテの影響を受けて、北イタリアのゴシック様式に古典様式を導入して融合を図った建築=彫刻家であるが、その個性的な特徴は一目見てわかる華麗な装飾性であり、すなわちファサードは赤と白の大理石の市松模様で装いを凝らし、中央の薔薇窓のほか精緻に細工された小アーケード、メダイヨン、浮彫などで飾られている。こうした綿密な工芸性は、彼がそれより後に制作した有名なチェルトーザ・ディ・パヴィーア(パヴィーア郊外のカルトゥジオ会修道院)においても発揮されているもので、一歩間違えば嫌悪感を招きかねない饒舌さには、たとえばアッシージのフランチェスコ聖堂の清楚な美意識と比べてなんという違いだろうかと驚かされてしまう。要するにローマの古典に直接の典拠を求めたブルネレスキやブラマンテと異なり、アマデーオによって代表されるロンバルディーア・ルネサンス建築は、地方的なゴシックの伝統を捨て切れていないということができよう。なおコッレオーニ礼拝堂の内部には、アマデーオが制作したバルトロメーオとその愛娘メデーアの石棺彫刻が安置されている。
〔4〕近代のベルガモ:「低い都市」
現代のベルガモ市の政治・経済の中心は「低い都市」の方である。人口の増加に伴う「高い都市」から麓の平野に向かう拡張は、すでに中世後期に始まっていた。すなわちこの時代に急速に発達した商業に従事する人たちが南側に新しい居住区(ボルゴborgo)を形成する。それはいまでも「ボルゴ」のつく地名として一部に名残を止めているが、borgo(フランス語 bourg)とはもともと一般的に西欧の中世自治都市の市壁の外縁に発生した新市街で、「ブルジョア」という言葉が borgo の住民である「新興市民」から「金持ち」という意味に転用されて行く過程は、つねに農民を疎外した近代資本主義経済の発展の様相を示すものにほかならないだろう。ベルガモの初期の borgo には商人や手工業者たちの質素な住居や馬小屋、荷車置き場などがひしめき、ささやかな教会堂もあったと思われるが、それらは全く残っていない。しかし15世紀にヴェネツィアが支配するようになってから「低い都市」は都市計画的に整備され、ベルガモの活動の中心はこちらに移動することになる。「高い都市」に住む上流階級の中でも下に降りて豪壮な邸宅を構えるものも現れ、ルネサンス様式の格調ある聖堂もいくつか建立された。
「低い都市」の発展において最も重要な出来事は、1738年、現在のボルゴ・ピニョーロ Borgo Pignolo のあたりに大規模な公営市場(Fiera)が開設されたことである。それは三二棟の建物の中に五四〇の店舗を擁し、全体を塀で囲ったもので、各種の商品が取引されたほか、夏期にはいわゆる見本市が開催され、イタリアの他の都市はもとより、アルプスを越えてスイス方面から多数の商人が参集したといわれる。しかし20世紀の初めには取り壊され、ミラーノの新設された国際見本市会場に貿易のセンターが移った。
そもそも中世のロンバルディーアはヨーロッパにおいて最も人口が多い地域であったと考えられる。度重なる戦乱と二度にわたるペストの災害を乗り越えて、経済が大いに発達した。15世紀には羊毛の加工と、とりわけ絹織物の生産が活発になる。コーモから奥の山地で桑の栽培による養蚕が行われ、ベルガモでは年間360梱の絹を産出し、ヨーロッパ各地に輸出された。シルク・ロードによって東洋からもたらされて珍重された絹織物が独自に生産されることになり、それを独占していたのがベルガモのほか、ミラーノ、ブレーシャを中心とするロンバルディーアだった。現在ファッションの発信地としてあまりにも有名なミラーノの繊維産業の基礎はこうして築かれていったのである。さらに、アルプスを背景にして鉱業がつねに盛んであり、金属を用いた武器の製造が大いに振るった。そんなわけで、ベルガモで貨幣が鋳造されていたことはすでに述べたが、当然のこと金融業も発達し、「ロンバルディーア人 lombardo 」という語がいつの間にかすなわち「銀行業者」の同意語となる。現在もロンドンの金融街として知られる Lombard Street の由来もそこにあるというからおもしろい。
〔5〕ヴェネツィア派絵画の拠点
ベルガモの「低い都市」で最も重要な文化施設といえば、「高い都市」の東端のサンタゴスティーノ門を降りてすぐのあたりにあるアッカデーミア・カッラーラAccademia Carraraである。18世紀の富裕な地方貴族、ジャーコモ・カッラーラが遺言によって寄贈した美術コレクションを展示する絵画館(ピナコテーカ)と美術学校の総体である。建物は1810年に新設された。1958年に私立の財団からベルガモ市が運営を引き継いでいる。学校の方はともかく、絵画館は展示室は二二、所蔵作品数は一六〇〇というこじんまりとしたものとはいえ、収集の基準と質の点において、イタリアでも屈指の美術館ということができる。内容としては、北イタリアの国際ゴシックに始まり、15世紀から19世紀までのイタリア絵画が大部分を占め、ほかにデューラーやルーベンスなどの北欧の画家が数点含まれるのみである。(例外的にこの地で生まれた20世紀彫刻の巨匠マンズーを記念する特別展示がある。)注目すべきことは、分類上いわゆるヴェネツィア派の範疇に入る画家の数が圧倒的に多いことであり、ヴェネツィア派のコレクションとしてはヴェネツィアそのもののアッカデーミア美術館に次ぐ充実ぶりなのである。このことは、先にもちょっと触れたように、15世紀にベルガモがヴェネツィア共和国に編入されたことと大いに関係するのだが、これは文化史的にユニークな現象なので、その状況を少し仔細に検討してみよう。
イタリア北部のほぼ同緯度上に並ぶミラーノとヴェネツィアは、現在でも幹線道路と鉄道で一直線に結ばれているが、15世紀にこの二つの勢力は熾烈な抗争を繰り広げていた。繁栄の絶頂を迎えたヴェネツィアは、ヴィスコンティ家の支配下にあった西に向かい、1405年にはパードヴァ、ヴェローナを奪い、1428年にはブレーシャ、そしてベルガモを傘下に収めることになる。しかしそれ以上の西進はなかったから、ベルガモはヴェネツィア共和国の最西端の領地ということになる。もともとランゴバルドの血を引くベルガモは、文化的にはミラーノの影響を強く受けてきたことは自然であるが、16世紀を境にして、人種的にも異なるヴェネツィアの主導のもとに入るというドラスティックな変化が生じ、美術の分野に絞っていうなら、途中にあるパードヴァ、ヴェローナよりももっと遠いベルガモに、ヴェネツィア・ルネサンスが波及するのである。
アンドレーア・プレヴィターリ<受胎告知> 1500~12 油彩、板、チェーネダ サンタ・マリーア・デル・メスキオ聖堂
アンドレーア・プレヴィターリ <聖母子> 1513 油彩、画布 ベルガモ アッカデーミア・カッラーラ
ジョヴァンニ・カリアーニ <十字架を背負うキリスト> 1510~14 油彩、板 ベルガモ アッカデーミア・カッラーラ
ジョヴァンニ・カリアーニ <フランチェスコ・アルバーニの肖像> 1516~17 油彩、画布 ロンドン ナショナル・ギャラリー
15世紀のベルガモの美術は、当然のことながらロンバルディーア派といわれるグループの活動の範囲内にあった。すなわち、ミラーノに本拠を置いてパヴィーアなどで活躍していたベルゴニョーネ Bergognone(本名Ambrogio da Fossano)は、「低い都市」にあってベルガモのルネサンス様式を代表するサント・スピリト聖堂に聖母子像を中心とする祭壇画を制作し(1507)、そのほか名前だけをあげると、シピオーニ、ボゼッリ、マリノーニ、ブイトーネといった地方画家たちが仕事をしていた。忘れてならないのは、15世紀の末、スフォルツァ家の招きを受けて、ブラマンテとレオナルド・ダ・ヴィンチがミラーノに滞在していたことであり、つまりロンバルディーアのルネサンスはこうしてフィレンツェとローマからもたらされたものであった。ベルゴニョーネに見られる古典的秩序が彼らの影響であることは明らかであり、もし「ベルガモ派」という範疇を設定するなら、それは極めてマイナーなものであることは否めない。
そうした状況の中でおもしろいことが起こる。ベルガモおよび周辺出身の画家たちが「首都」ヴェネツィアに移り住み、ジョヴァンニ・ベッリーニに続き、ジョルジョーネとティツィアーノが君臨する画壇で成功を収め、「故郷」からの注文に応えて作品を送る者が現れるのである。比較的重要な名前だけをあげると、アンドレーア・プレヴィターリ Andrea Previtali(図4、5) 、ジョヴァンニ・カリアーニ Giovanni Cariani(図6、7)などである。この二人はいずれもベルガモといっても北西に十数キロ離れた山間部の出身で、しかも後者はヴェネツィアで官吏として出世した父親に同行したという事情があったのだが、それにしてもこの時代の美術の最前衛がヴェネツィアであったという状況が浮かび上がる。このようにしてヴェネツィア・ルネサンスがベルガモに移入された。
このことに関して、1513年に決定的な出来事が起こる。ボルゴの一角にあったドメニコ会のサント・ステーファノ聖堂(1561年の新しい城壁築造の際に撤去されて現存せず)のための祭壇画のコンクールが催され、ヴェネツィアの画家ロレンツォ・ロット Lorenzo Lotto が制作者として選ばれたのである。美術制作のコンクールはすでにフィレンツェの有名なサン・ジョヴァンニ洗礼堂の扉の浮彫などで行われ、美術の公共性という点についての画期的な制度が生まれようとしていた。この場合、いわゆる指名なのか公募なのかは不明なのだが、すでに前年にベルガモに帰郷していたプレヴィターリも参加し、こちらは落選したことが記録で知られている。コンクールを主催したのはヴェネツィアの忠臣的な騎士だった前述のバルトロメーオ・コッレオーニの息子、マルティネンゴ Martinengo であった。(以後ロットのこの作品を<マルティネンゴの祭壇画>と呼ぶことになる。)実はサント・ステーファノ聖堂にはすでにベルゴニョーネの祭壇画が飾られてあったのだが、それを廃棄して新しいものに変えようとしたのである。それは明らかにこの時期のベルガモの政治的状況と密接に関わっていることである。
15世紀末から16世紀中葉までの半世紀は、イタリアの覇権をめぐってフランス、スペイン、ドイツなどが争い、それに教皇庁やイタリア諸侯が介入するいわゆる「イタリア戦争」という混乱した時代であった。この間ベルガモはフランスとスペインの双方から頻繁に占領されるが、1515年頃には最終的にヴェネツィアが奪回する。ところで前述の1513年の時点で、ベルガモではフランスのルイ12世の支配下にあったミラーノを支持するいわば守旧派と新進のヴェネツィア派とに市民勢力が分かれていた。ベルゴニョーネはミラーノ派を代表する最後の画家だったのである。サント・ステーファノ聖堂の多翼祭壇画(現在アッカデミーア・カッラーラ蔵)を見ると、キリスト像をはじめとする主要部分をこの際措くとして、下部の左右にフランス王ルイ9世(聖王ルイ)(図8)と聖ヴィンチェンツィオ(ヴァンサン)の像が大きく描かれている。ルイ9世は決闘や賭博を禁止するなどしたことで知られる名君で、その後聖人として崇められるが、その像は濃い青地に金色の百合の花の紋章をあしらった祭服を着た姿で表され、王が十字軍遠征で発見したとされるキリストの茨の冠を手に持っている。百合の花はルイ9世のアトリビュートであり、その後フランスそのものの象徴ともなった。また、聖ヴィンチェンツィオはスペインの3世紀の殉教者だが、なぜかフランスでその崇敬が広まっている。つまりこの祭壇画がフランスの宗教的風土を代表していることは歴然としているのである。ベルガモのドゥオーモについて書き落としたことだが、この聖堂も初め聖ヴィンチェンツィオに捧げたものである。
一方ロットの<マルティネンゴの祭壇画>(サン・バルトロメーオ聖堂蔵)は一枚の大型画面の形式で、建築空間の中に聖母子が置かれたもので、特にヴェネツィア的要素を強調するような図像が用いられているわけではないが、ルネサンス様式の特徴を十全に発揮した表現である(図9)。ロットの芸術についてはさらに後述するが、その後1525年まで12年間ベルガモに留まり、いくつもの教会のために制作した。そしてプレヴィターリも同様に、28年に病死するまで活躍し、もう一人のカリアーニも1517年には帰国して23年まで滞在した。こうしてベルガモの美術環境は完全にヴェネツィア派が制覇することになった。2001年にアッカデーミア・カッラーラで催された「もう一つのヴェネツィア」(L'Altra Venezia)と題する特別展には「ロレンツォ・ロットの時代、1510-1530のルネサンス」という副題がつけられ、この明確なコンセプトのもとにアメリカを含む各方面からの作品が集められて展示された。ロットに加え、プレヴィターリとカリアーニの三人を主役とみなし、20年間にベルガモで起こった特異な文化的状況に光を当てている。たとえば宗教的思想によるのではなく、純然たる政治的動機によって、これだけあからさまな様式の交替が生じるのは美術史においてまれなことだろう。
〔6〕黒の画家ロレンツォ・ロット
さてロレンツォ・ロット(1480~1556)とはどんな画家か。私は1967年に初めて、ローマのボルゲーゼ美術館で彼の二点の作品を見てなんとなく頭に引っかかった。それまで名前しか知らない画家だったのに、黒の使い方が印象的だったのである。その後デ・キリコの自伝を読んでいたら、一癖あるこの形而上派の画家が、興味をもつ作家の一人としてロットの名をあげていたのでわが意を得た思いがした。事実、バーナード・ベレンソンが注目して1895年に研究を発表するまで、ロットは美術史界で長い間忘れられていたといっていい。生涯の作品数は379点とされているが、所在地は各地に分散し、まとまったコレクションがないから、その全貌を知ることは容易ではないのである。・・・・・・ロットはヴェネツィアで生まれ、この地の美術界を主導していたジョヴァンニ・ベッリーニやアルヴィーゼ・ヴィヴァリーニの影響を受けて出発するが、それらのもつ形態や色彩の均衡を打破した、より動的な独自の作風を作り上げた。1509年にはローマに招かれてヴァティカーノ宮殿のユリウス2世の居室に壁画を描いたりするが(現存せず)、このローマ滞在の間にラッファエッロらと交流があり、古典的な美術の伝統を知ってさらに自分の芸術を成熟させたと思われる。ベルガモに滞在する間、前述のコンクール作のほか、サン・ミケーレ・アル・ポッツォ・ビアンコ聖堂のフレスコをはじめ、サンタ・マリーア・マッジョーレ聖堂では聖職者席の寄木細工の下絵をかき、これは規模の大きさからしても、質の高さからいっても、ルネサンスの寄木細工の最高の傑作であるし、その他の現存する四つの聖堂の祭壇画を制作した。そのほか多くの肖像画を引き受け、それは各地の美術館に収められている。ベルガモを去った理由はよくわからないのだが、その後はマルケ州などを転々として制作を続け、最後は精神異常をきたしてロレートの修道院で歿した。このように、ロットの最も充実した時期がベルガモの12年間だったのであり、ヴェネツィア派の画家と位置付けるにはあまりにもアウトサイダー的存在だったといえるだろう。
ロットの芸術について、ことに「冷たい色調」あるいは「暗色」への固執はすべての美術史家が一様に指摘する特徴であるが、私にいわせればずばり黒色の嗜好であり、いくつかの肖像画では黒バックの前にさらに黒の衣服を着た人物を置いているのだから驚かされる(図10,11,12)。
黒という色はいまでこそ最高に優雅な色として好まれているが、常識的に考えて、ルネサンス時代の世俗社会の華麗な色彩感覚とはほど遠い。肖像画において背景に自然の山野や建築空間を描くのでなく、図像的にニュートラルな黒バックを使用することは、まさに1520年代頃のラッファエッロなどにも現れ、流行のように広がって行くことが認められる。いったい最初に発案したのはだれかという検証はきわめてむずかしい問題だが、1495年頃ヴェネツィアに滞在していたドイツの画家デューラーも黒バックをしきりに用いており、ロットがその影響を受けたという可能性もある。つまり黒は北方的な感性に適合し、図式的にいえばイタリアの美意識には縁遠いということになるだろうが、ロットが黒を多用したことは単に色彩感覚の問題ではなく、距離的には非常に近いスイスで展開していた宗教改革の背景にある「不安」の時代精神を確実に表していることを、何人かの美術史家が示唆している。そして肖像画に限らず、たとえば<イエスの誕生>(図13)におけるように、夜の闇と聖なる光の激しいコントラストで劇的な効果を生み出す手法は、バロック絵画をある意味で先取りすることでもあった。いずれにせよ、晩年に報われずして貧困のうちに死んだというロットという特異な芸術家の人格と芸術について、もう少し研究が進むことを期待しよう。
ヴェネツィアとの交流に関して、絵画以外の話題を一つ書き加えておこう。16世紀末頃から成立した有名な大衆喜劇コンメディア・デッラルテに登場するアルレッキーノの仮面はベルガモで生まれたものである。このキャラクターはもともとアルルカンとしてフランスで生まれたらしいが、ベルガモ北方のブレンバーナ渓谷を50キロほど上ったサン・ジョヴァンニ・ビアンコ村のオネータ集落という所の粗末な家に遺された伝承によれば、初めて仮面をつけてその役を演じたのがベルガモ出身の芸人、アルベルト・ナゼッリという人であった。ヴェネツィアでもアルレッキーノはつねにベルガモなまりで台詞をしゃべっていたという。
〔7〕国際郵便のはじまり
中世のコムーネ時代の終わり頃から現れるベルガモの有力者たちの中にタッソ Tassoという名家がある。出自はやはりブレンバーナ渓谷のコルネッロという寒村で、13世紀半ばから家族の記録がある。その後ベルガモ市内に移り住み、16世紀の初めにはドメーニコとガブリエーレというこの一族のメンバーが現在のピニョーロ通りとタッシス通りに邸宅を構えていた。『フェッラーラ』の章で述べた詩人トルクアート・タッソも実はこの家系に属し、彼は父親の都合でソッレントで生まれて以来、南イタリアやフェッラーラで過ごしたけれど、後にベルガモを訪れたこともある。
しかしなんといってもタッソ家の重要な足跡は、15世紀に郵便事業を始めたことだ。まずは二大都市ヴェネツィア=ミラーノ間の郵便配達を引き受けることから始まり、ついでローマにも範囲を広げ、「ヴェネツィア共和国およびヴェネツィア=ローマ郵便会社」(Compagnia dei corrieri della Serenissima e della Venezia-Roma)というややこしい名称の組織を設立した。ローマでは教皇庁の信任をも獲得し、教皇の勅令をも含む重要文書をスペインにまで届ける役を担った。1502年、ジョヴァンニ・タッソの時に、神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世の委託を受けて宮廷とローマを結ぶサーヴィスも開始する。さらに弟のフランチェスコは本拠をブリュッセルに移し、フランツ・フォン・タキシスと名乗り、カール5世よりオーストリアとフランドルの郵便事業団長(Meister)の資格を与えられ、1541年に彼が死ぬと甥のジャンバッティスタに受け継がれ、フランクフルト、アウグスブルク、ヴィーン、インスブルック、ヴェネツィア、ミラーノ、ローマ、マドリッドなど、十数カ所の都市に「郵便局」を置くに至る。当初は各宮廷同士の公的文書の配送を委託されるというメッセンジャーのような役割だったわけだが、ほどなく一定の料金と引き換えに一般人の私信の配達も請け負うようになり、こうしてタッソ(タキシス)家による中部ヨーロッパ全域の郵便事業の独占体制が確立した。
それ以前の郵便の事情はといえば、古代はさておくとして、中世都市国家の場合はその都度「使者」が任命されて旅立ったものと思われ、またフィレンツェを始めとする商業都市の商人たちは交易の必要から私設の郵便配達団を抱えていたらしい。ある史料によれば、おもしろいことに、一般市民は肉屋に私信を託す習慣があったというが、肉屋は仕入れのために山間僻地まで赴くので便利だったからだと説明されている。輸送の方法は初めは専ら単独の騎馬行であったが、郵便量が増えるにつれて馬車が使われるようになり、それがやがて乗客をも乗せるようになる。タッソ一族は近代国家が成立するまでの三百年あまりの間、12代にわたり、この巨大産業を独占していたのである。
ついでながら、中世後期から、ベルガモ北方のアルプス山麓の住民たちは、よりよい暮らしを求めて都市に出稼ぎに行く習慣があったが、ヴェネツィアやジェーノヴァでは、頑健な体力にものをいわせて、港湾の労働に従事して評価され、特にジェーノヴァでは沖仲士組合を結成して存在感を発揮していたといわれる。こう見てくると、ベルガモ人はどうやらなかなか外向的な性格の持ち主のようである。しかし「高い都市」の静謐さや、「低い都市」の整然とした町並みから、一旅行者がかれらの素顔を見ることは難しいといわねばならない。もちろんそれはベルガモだけのことではない。
SPAZIO誌上での既発表エッセー ≪イタリア12都市物語≫ 目次
- ペルージャ――エトルリアからペルジーノまで no.55(1997年6月発行)
- モーデナ――ロマネスク街道の要衝 no.56(1997年12月発行)
- ピーサ――中世海港都市の栄光 no.57(1998年6月発行)
- パードヴァ――中世における知の形成 no.58(1999年4月発行)
- シエーナ――中世理想都市の運命 no.60(2001年3月発行)
- ヴェローナ――北方との邂逅 no.61(2002年4月発行)
- ウルビーノ――新しきアテネ no.62(2003年4月発行)
- マントヴァ――ある宮廷の盛衰 no.63(2004年8月発行)
- フェッラーラ――小さなルネサンス no.64(2005年7月発行)
- パルマ――フランス文化の投影 no.65(2006年6月発行)
小川熙さん 著書紹介

小川熙氏の「イタリア12都市物語」が単行本として本年1月30日に上梓されました。
『SPAZIO』誌上での連載を開始した1997年以降、SPAZIO自体の発行が年2回から1回になり、印刷物からWebに変わるという変遷の中、当シリーズの完結は大幅に長引いていました。そこで、昨年の10都市目「パルマ」が終わった後、二都市(今回のベルガモと次回のラヴェンナ)が加筆され、先に書籍出版されることとなりました。
なお、来年のラヴェンナをもって、SPAZIOとしての12都市を完結いたします。
単行本とSPAZIOともども、どうぞご愛読ください。